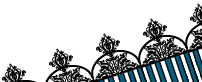「はあっ、はぁぁ…」
もう、頭の中がどうにかなりそうで目の前がオレンジ色に霞んだ。
俺の胸に合わさるトシの鼓動が、熱く熱く、なる。
「またイったな。近藤さん」
うっすら目をあけたら、笑うトシがいた。
ぞくぞくした。その熱く冷たい緑色の瞳に見られているというだけで。
目の下あたりを親指でなぞられ、そのままキスされる。
「知ってるか?」
キスのあと、髪が跳ねて少し幼いおもてになったトシが言う。
「中でイったら、もう他じゃあ満足できねぇんだぜ」
はぁ、と自然に息が漏れる。
耳の後ろを優しくて撫でられて、睫毛に唇を落とされて。
お伽噺の王子みたいなことをするのに、言ってることは全然違うし、やってることなんてまるでファンタジーとはかけ離れてる。
でもそんなトシが俺は大好きで、何度もいかされて鳴かされてもう無理っていってんのに離してくれなくても、俺みたい奴相手によくできんなぁ、なんて思うくらい。
「近藤さん」
トシの手の平が耳から離れていく。
今度は俺がトシの顔に触れようとしたら、逆手を取られて布団に押し付けられる。
ようやく落ち着いてきた呼吸が心音と共にまた荒くなって、俺は恥ずかしさと息苦しさで体の上のトシごと身動いだ。
「あんたもう、俺なしじゃいられねぇな」
滑り込む声はいつもより数段かっこよくて、俺の頭はドロドロに溶けていく。
ほんとやばい。俺、トシのこと好きすぎてどうにかなりそう。
縫い付けられている手首が熱くて、トシの肌も熱くて、もうなんか色々煮えそうだった。
「トシ」
耐えらんなくて思わず普通のトーンで声を出したら、いきなり唇を塞がれる。
やばい、本気でやばい。
さっきイったばっかなのに、欲しくて欲しくてたまらない。
「ん…トシぃ」
もぞもぞ動いてそれを知らせると、またあの射抜くような視線を向けてくる。
「欲しいって言えよ。近藤さん」
態勢を変え俺の上に馬乗りになったトシの濡れた性器に、俺の目は釘付けになった。
今すぐ欲しい。溶けそうになるくらいぐちゃぐちゃに突いて、掻き回して欲しい。
なのに俺のくちは閉じたまんまで、欲しいものを欲しがる言葉は出てこなかった。
何を今更躊躇っているのか自分でもわからないのに、体だけは正直でどんどん熱は上がっていく。
「ん? 言えないのか? 近藤さん」
「は、は…も、いやだ」
苦しい。辛い。早く欲しいのに。
目をつむると、影が落ちてきて頬を熱い指が撫でだ。
「全く…」
ため息と一緒に呟かれた声に思わず目を開けると、予想と反して優しい顔をしていた。
ふあ、と間抜けな声が出る。
「泣くなよ。もっと苛めたくなる」
「え…?」
俺はそう言われて初めて、自分が泣いていることに気付いた。
オレンジ色に霞むトシが俺の手首を解放して、長い指で目の下を拭う。それがあんまり優しいから全然涙は止まらない。
「なんで」
もうほんと嫌だ。泣くとかありえない。
ついでにまだ欲しがってビンビンなのもありえない。恥ずかしい。
「ほら、悪かったって。んん」
唇を突き出してキスをしてくるから、ますます居たたまれなくって「トシ」と小さく呼んでみる。
足の指を無意味に曲げたり伸ばしたりして何とか涙を止めようと頑張ってみるけど、全然だめだった。
トシがほっぺたやオデコにキスをしてくれて嬉しいのに、それ以上に恥ずかしさが勝ってしまう。
「ごめん、俺」
「謝んなよ。もう苛めたりしない」
「そうじゃなくて…」
俺、全然トシの期待に応えられてないのに、何で嫌な顔ひとつしないで許してくれるんだろう。
もう嫌だ。こんなの俺じゃない。
どうしてこいつは俺に優しくするんだ。
「ちゃんとイかせてやるから」
「違う…違う、俺は」
ずっと俺の上に跨がっていたトシがどいて、毛布をかけてくれる。
ああもう、期待どころか失望させてばっかりだ。
「落ち着いたか?」
お伽噺の王子様は持続中なようで、トシは弱く髪を撫でる。
横目で見ると微かに困ったように笑うから、俺はますます居たたまれなくなった。
「朝から忙しかったもんな」
「…うん」
確かに忙しかった。でもそれは理由じゃない。
怖いんだきっと。いつだってすごく怖がってる。トシが好きだし、だからこそセックスでだって満足させたいのに。
「今日は、入れないから」
「え、でも」
「無理させたくないんだ。どうしたってあんたに負担かけちまうしな」
「……っ」
だめだ。
きっと俺はいつか、トシの優しさを裏切ってしまう。
「なんで!」
オレンジ色に霞む世界が、更にどんどん霞んでいく。多分、遅かれ早かれこうなることになるって、俺はわかってた。
大人同士で、男同士。言葉にすれば簡単だけど、実際はすごく複雑で難しい。
トシは気にすんなって言ってくれるけど、でも、考えるんだ。
いつか二人が別々の道を歩むことになったとき、俺はもう普通の恋愛も結婚もできない。
「そうやっておまえが優しくするから…っ」
優しくするから?
トシのせいにするのは、ただの責任逃れじゃないか。それは分かってる。分かってるのに。
がばりと起き上がって、結局何もできずに止まらない涙を流すままにする。
「なんでこんな」
「おい、ちょっと待てよ近藤さん」
手の平で覆った顔はとてもあげられない。
耳も塞ぎたい気分だった。
「俺は…優しくなんかしてないよ」
……?
すぐには言葉の意味をを理解できずに、俺は指の間から横を見る。ちょうどトシが近寄ってくるときで、あ、と思った瞬間には背中から抱き締められていた。あったかくて、すべすべしてる、トシの胸板。
「やりたいことをやってんだ」
「やっ、やだ…」
耳元で吐息のように囁かれて、トシがぴったりくっついてる背中に、ぞくぞくって電気が走った。
ちょっとだけ萎えてた気持ちが一気に頭を支配していく。
「もうとっくに分かってると思ってたが…計算違いだったな。あんたの鈍さを忘れてた」
「……」
「だからもう、おかしな考えは捨てろよ。あんたが望まない限り、俺はここからいなくならない」
優しい、優しいトシ。
おまえはそんなんでいいのか。
人並みのしあわせとか、そういう、人生の最後に笑える生き方をしたいって思わないのか。
なんでよりにもよって俺なんだ。
いっそ嫌いになれたら、トシを傷つけてでも正しい道に戻せたのに。
「…全く、あんたの頑なさには呆れるな」
「ご、めん」
ふう、と息を吐いて、トシは後ろから俺の肩に顎を乗せ、わきの下から腕を伸ばして腹の上で指を組んだ。
その上から手のひらを重ねるとうなじの辺りに音を立ててキスされる。
「なあ、現実はあんたが考えてるほど難しくないんじゃねぇの」
トシはそう言って毛布をひらりと被り、俺ごと包み込んだ。ちょっと尺が足りなかったけど、トシの体温とですごくあったかい。
まだ濃く残る精の匂いが、冷えた頭には恥ずかしいけど。
「俺達はただの恋人同士だ。それでいいじゃねぇか」
「…うん」
「そこらじゅうにいる二人とどこが違う? なんにも変わんねぇよ」
う、と声が出そうになって耐えるけど、やっぱり無駄だった。お伽噺の王子は、こんな俺でもいいって言ってくれて、こんな俺を愛してくれてる。
こんないい男、なかなかいねぇよなって思ったらまたもや泣けてくるから困った。
いつからこんなに涙もろくなったんだろう。
「泣くなよ。ったく、あんた最近泣いてばっかりだな」
「うん…ご、ごめ」
ひく、と子供みたいに嗚咽を漏らした俺を、トシが更に優しく抱き締めてくれる。
霞むオレンジ色の中、俺はでも、やっぱり思った。
いつかもしトシがいいひとを見つけて、俺の下から去っていっても、俺はずっとトシが好きなんだろうって。
なぁトシ、俺は、本当になんて幸せなんだろう。
「よし、寝るか」
ぱんと俺の肩を叩き、毛布を脱いだトシの腕を、俺は掴んだ。
はっとしたようにこっちをみた目を見返して、裸のままの腹の顔を近づける。
「まだ、時間あるし」
「…近藤さん」
「いいよ。俺は…俺も…したいから」
近藤さん、ともう一度聞こえたときには真正面にトシの顔があった。
は、と熱い息が喉のあたりにかかる。
「トシ」
絞り出した声は果たしてトシに届いていたのか、口にぶつかった唇に、俺の言葉は阻まれる。
目をつむると好きだって聞こえたから、俺も好きって言った。
ああ。生きてる限り俺はおまえを、ずっと好きで居続ける自信があるから。
大好き、ほんとに大好きだよ。
「ごめん、…」
トシの低い声が揺れる。
うん、と言ってキスしたらもう――夜の音は聞こえなくなった。
おわり
- 10 -
戻る