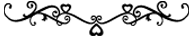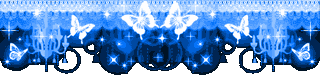

『炎真ッ! このままじゃ了平が死んでしまう!』
『獄寺君を助けてよ、ボスッ!』
『ランボさんもっ!』
『山本が大変そうで……』
『オレちんのクロームちゃんが汚される!』
『炎真、沢田を何とかしろッ!』
守護者達の切なる懇願を受け、炎真は疲れ果てながらも沢田の執務室へと向かっていた。
ボンゴレ守護者達がどんな状態になっているのか……それはもう聞くだけでうんざりしてしまうもので。
しかもその原因が自分にもあるという理不尽さも、炎真にとっては泣きたい要素の一つだった。
中学時代の頃とは違い、今や双方とも立派なマフィアのボス。
私情を優先することができない立場にいる、その自覚はあってもいいはずなのだ。
しかし……沢田にそんな理屈は通用しないらしい。
「……此処、か」
重厚な扉の前まで来ると、炎真はピタリと足を止める。
扉にはボンゴレの紋章が刻まれており、中からは人の気配がした。
軽く扉をノックすれば、そのまま両手で押し開ける。
瞬間――何かに飛びつかれ、炎真はバランスを崩した。
「わっ!?」
「久しぶり〜!」
満面の笑顔で、今回の元凶――沢田綱吉は嬉しそうに炎真に抱きついている。
間一髪で扉に直撃しなかったが、打ちつけた背中が少しだけ痛い。
けれど、毒気を抜く無邪気な子供の顔は、怒る気力を根本から削ぐようだ。
炎真は甘えてくる沢田の頭を撫でた。
猫のように擦り寄ってくる愛らしさは、どうしても無害にしか見えない。
「もうツナ君ってば……こんな危ないことして怪我したらどうするの」
「炎真君なら受け止めてくれるって信じてたし」
「そういう問題じゃないでしょ。ほら、退いて」
「いーやー」
くすくすと笑って尚も甘える様は、はっきり言ってドン・ボンゴレの威厳など欠片もない。
本人にしてみればどうでもいいことなのだろう。
沢田にとって、炎真が此処にいるということが何よりも重要なのだ。
小悪魔的仕草に流されそうになった炎真だが、自分が此処に来た理由を思い出して優しく問い掛ける。
「ねえ、ツナ君。何であんな事したの?」
「あんな事って?」
「皆に無理難題押しつけて……それがボスのやること?」
炎真は柔らかく訊ねたつもりだったが、沢田は黙って俯いてしまう。
都合が悪いと沈黙を貫くのが沢田の常でもあった。
大抵は根比べとなって炎真が負け、何もかもが有耶無耶にされて終わる結果となる。
だが、今回ばかりはよくないと思ったのだろう。
炎真は一歩も退かず、沢田の答えを辛抱強く待った。――そうして長い長い時間が経った後、観念した沢田はか細く言葉を呟く。
「……炎真が悪いんじゃないか」
「半年以上会えなかったことを言ってるの? でもそれは「それだけじゃないよっ!!」
急に顔を上げた沢田を見て、炎真は言葉を失う。
琥珀の瞳は潤み、ぐにゃりと歪んだ顔からは、言葉にしても足りないぐらいの哀しさや切なさが伝わってきた。
「炎真はいつだってシモンの皆が大事なんじゃないかっ! たまに電話をくれた時だって、楽しそうに彼等の話をしてっ!! オレは炎真とずっといられないのに、彼等は家族だから一緒にいられて……それなのに、貴重な二人の時間まで邪魔して……っ。オレは炎真のものだけど、炎真といるためならどんな努力でもするけど、炎真はオレのものじゃないしオレよりシモンの皆を選ぶじゃんかっっ!!」
溜まりに溜まった不平不満を、沢田は喚き声に乗せて一気に撒き散らす。
堰を切ったように溢れだした涙が、炎真の顔の上にいくつも落ちた。
堪えていたはずの、鬱憤を晴らす形で八つ当りして抑えていたはずの、だけど何よりも伝えたかった――本音。
「ツナ君……」
炎真は何かを言いかけたが、すぐに口を閉ざす。
きっとどんな言葉も慰めにはならない。
何より、炎真は沢田がここまで嫉妬深いことを知らなかった。
どんな思いで電話に出ていたのかも、相槌を打って馬鹿笑いしてくれていたのかも、何も何も……知らなかった。
言ってくれればよかったのに……なんて思ったところで、沢田がそういう性格なのは炎真自身一番良くわかっていた。
どんな感情も、溜め込んで溜め込んで、最後には一気に爆発して周りを巻き込む。
そういうタイプだということは、付き合う前からわかっていたはずなのに……。
「……ああ、そっか」
ふと、何かを思いついたように沢田が呟く。
自嘲にも見える笑みは、炎真の不安をいっそう掻き立てた。
「炎真君、優しいもんね。オレが押しつける形で告白したから、断り切れなかっただけなんだぁ」
「っ!? そんなことないッ!!」
「いいよ、もう。浮かれてたのオレだけだったわけ「だから違うってば!!」
半ば怒鳴りつけるように否定し、炎真は沢田を力強く抱き寄せてから唇に口づける。
振動で背中の痛みが響いたが、そんなことを気にしている場合ではなかった。
唇が離れれば、沢田は信じられないといった顔をして炎真を見つめている。
「え、ん「ばか。僕はそんないい加減な男じゃないよ」
琥珀の瞳、紅玉の瞳。
二つの視線が絡み合い、甘やかに見つめ合う。
先に堪え切れなくなった沢田は顔を背けようとしたが、炎真に後頭部を抑えつけられて叶わなかった。
それだけでも拷問だというのに、炎真の精神的攻撃はまだ終わらない。
「だけど、今回は僕も悪かったよ。次からはちゃんと定期的に会いに来るから……ね?」
「べっ、べつにそんなわざわざ「――愛してるよ、綱吉」
「っ!?」
耳元で囁かれ、沢田は顔を真っ赤にして狼狽える。
唇をパクパクとさせ、鼓動の高鳴りが異常を訴えていた。
普段自分が押していくタイプだから、受ける側に慣れていないのだろう。
炎真が滅多なことでは直接口にしないのも、動揺する要因の一つかもしれないが。
しかし炎真は無自覚でこの行為に及んでいる。
無意識、と言ってもいいかもしれない。
「あれ? ツナ君、顔まっか「わーわーあーっもうっいいのっほうっといてっ!!」
きょとんとしている炎真とは対照的に、沢田は必死に平常心を取り戻そうとしながらも騒ぎまくる。
その原因を作った相手は、不思議そうに首を傾げるばかりで。
――斯くして、マフィア界始まっての珍事件は幕を閉じたのであった。
fin
- 19 -