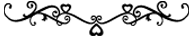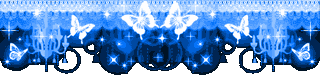

インスパイア元→巡音ルカ『硝子細工』
★★★★★★★★★★
「ツナ、お前……笑わなくなったな」
――ふと、死神が呟く。
さも今思ったような、そんな素振りを見せて。
「ん? あー……オレが笑うの、嫌う人がいるからね」
執務机で書類に向かっていた子供は、困ったように乾いた笑みを浮かべる。
笑い方が下手というより、今自分がどんな顔をしているのかわかっていない可能性の方が高い。
その様は、昔を知る者にとってはあまりにも不自然すぎた。
「嫌う人?」
「うん……彼には嫌われたくないんだよね」
控え目に、そうして遠くを見据えるような眼差しを向けて。
子供の透き通るような表情は、時折グラスのような蒼白を思わせた。
まるで血が通っていないような、生きていないような……。
華奢な双肩に伸し圧かる業は重く、いつか潰れてしまいそうにも見える。
それを防ぐための仲間はいれど、子供は昔ほど皆に頼ることは少なくなったかもしれない。
一人で抱え込むようになった……と言うべきか。
『仲間だって、ましてや僕だって、ツナ君にとっては必要ないじゃないか。痛みを隠して笑い続けるなら、いっそのこと独りになってしまえばいいッ!!』
「……独り、ね」
過去の言葉を思い出し、子供はぽつりと洩らす。
一番嫌われたくない人に、大切な人に、言われた言葉は刃物と化して心を突き刺し抉って。
あれ以来、子供は笑うことを止めてしまった。
心からの笑顔だけでなく、作り物の、硝子細工の笑みでさえも……忘れてしまったのだ。
昔、自分はどんな風に笑っていただろうか。
思い出そうとしても、子供の頭の中には靄が拡がるばかりで、何も浮かび上がってこなかった。
そもそも、自分が心から笑っていた時なんてあっただろうか……。
遠い遠い思い出の日々は、存在を疑うほど色褪せてしまっていた。
別世界に行って心ここにあらずの子供に向け、死神は引き戻すための言葉を投下する。
――ソレが、爆弾とも知らずに。
「そういや……今日はシモンが来るんだったな」
「え?」
「忘れたのか? 鈴木アーデルハイトが、天下のボンゴレの鍛練の様子を拝見したいとか言ってたじゃねーか。まあそんなモンは建前で、交流を深めるためってのが妥当な理由だろうがな」
見え見えの本心に、死神はククッと笑う。
――鈴木アーデルハイト、シモンファミリーのボスの補佐。
彼女は以前から、マフィアの頂点に立つボンゴレを見学したいと頼んでいた。
彼女曰く、過去に自分達が負けたのは日々の修業が足らなかったから、だと。
そのため、ボンゴレではどんな訓練をしているのか大変興味を持ったというのだ。
向上心の強い彼女らしいと言えば彼女らしいが。
頼み方も低姿勢だったため、ボンゴレボスの右腕は機嫌良く承知し、その訪問日が今日となっていた。
死神の言う通り、親睦を深めるためというのも少なからずあるかもしれない。
過去に確執があった二つのファミリーは、今では良好ともいえる関係になっていた。
その最たる代表として、ボンゴレ嵐の守護者とシモン沼の守護者は非常に仲が良い。
まるで幼い頃から一緒にいたかのように、気楽で親しげな雰囲気を醸し出しているのだ。
子供にも訪問の情報は回っていたが、今の今まですっかり忘れていた。
「あー……今日だったっけ。オレ、逃げようかな」
「馬鹿言ってんじゃねえ。ボスのお前が不在じゃ示しがつかねーだろうが。皆別々に移動するだろうから、おめーの所に来るのは必然的に……」
コンコン
控え目にドアをノックする音が外側から響く。
子供は舌打ちをすると、立ち上がって背後の窓の方を振り向いた。
そのままグローブをはめようとしたが――無機質な冷たさが後頭部に突きつけられれば動きが止まる。
その正体は、死神の愛用している拳銃の銃口だ。
数多の人間に死をもたらしてきた、形態を変えた死神の鎌。
「逃げようとか考えてねえだろうな、ボス」
「……」
脅すような声を背後に聞けば、子供の頬を冷や汗が伝う。
ここで実力行使に出ることもできたが、下手な真似をすれば確実に発泡されるだろう。
冗談だと頭ではわかっていても、それを心から信じられるほどお気楽思考ではなかった。
「……できれば逃げたいんだけどね」
「地獄にか?」
意地悪く問う死神は、引き金に指を掛ける。
口の端を吊り上げる様は、愉快で仕方がないといったところか。
子供は冗談抜きで身の危険を感じ、両手を高く挙げて降参の意を示す。
「わかった、わかった。相手すればいいんでしょ」
「最初からそうしろ。ダメツナが手間掛けさせやがって」
死神は悪態をつき、銃を懐にしまった。
子供はほっと一息吐くと、緊張して震えていた両手を下ろす。
寿命が延びた気分だと内心で毒づいて。
子供が嫌々ながらも振り向けば、死神は視線をドアの方へ移して声を掛ける。
「いつまでそこに突っ立ってんだ? 入ってきて構わねーぞ」
――促す台詞、戸惑う気配。
暫しの逡巡の後、意を決したかのように静かにドアは開かれた。
姿を見せたのは、頬にいくつか絆創膏を貼った赤髪の青年。
紅の瞳は長すぎる前髪に隠され、その表情は伺えなかった。
「取り込み中だった?」
「いや、もう終わったところだ。精々ダメツナのダメっぷりを見学して帰るんだな」
厭味を含んだ台詞を残し、死神は靴音を鳴らしながら立ち去る。
入れ替わりに青年が部屋に踏み入れれば、子供は相手の目の前まで移動して口を開いた。
「こんにちは。ドン・シモン」
何の感情もこもっていない、義務に近い挨拶が零れ落ちる。
表情は無表情とも呼べ、わざと心を殺しているように見えた。
青年はその様に胸の奥が痛み、同時にやるせなさまでも沸き上がる。
無理矢理心に蓋をしたが、いつ吹き出してもおかしくない状態だった。
「……今日はごめんね。無理を言って」
「気にしないで。シモンの皆なら歓迎するよ。多分大して参考にはならないと思うけどね」
肩を小さく竦める子供は、決して口元を撓ませることがなかった。
否、笑いかけることができなかった……というのが正しい。
「アーデルにしては苦し紛れの口実だったね」
「半分は本心だよ。十年前に敗れたことが相当悔しいみたい。きっとボンゴレでは毎日死ぬ気で特訓が行われているんだ……とか、まあ雲の守護者の人に負けたことが一番許せないんだろうけど」
「粛清の腕章取られちゃったしね」
「……うん」
さらっと言って退ける子供に、青年はただ複雑な表情で返した。
こんな素っ気ないやり取りとぎこちなさだが、一応二人は世間でいう恋人同士の間柄だ。
しかしその関係は誰にも知られておらず、本人達も表沙汰にはしない。
立場以上に、そうできない理由があるからなのか……。
「ねえ、ツナ君。君は変わったね」
「え……んっ!?」
青年は一瞬にして子供の細い腕を掴む。
逃げられないように力を入れれば、形だけは綺麗な唇に口づけた。
反射的に瞼を閉じる子供を見つめながら唇を離し、空いている手をそっと頬に寄せる。
見えない傷口を探すように、見えない血を探すように。
しかし子供は青年の手を払い、無理矢理微笑もうとする。
作りたくないと、嫌われたくないと、強く強く思っているはずなのに。
「……ツナ、君」
「ご、ごめん。つい癖で……エンマ君、オレの笑った顔嫌いなのに」
「ちがっ、そうじゃないっ!!」
間違って意味が伝わっていたことを知り、青年は強く強く否定した。
どうしてこんなにも極端なのだろう。
彼の笑顔が嫌いなわけじゃない。
一から十まで言葉にしなくたって、わかってくれるだろうと、そう思っていたのに……。
「僕は君の笑顔を嫌いだって言ったわけじゃない」
「……うそ、だって俺が笑ったら君は「それは溶けない氷のような笑顔で、君の本心じゃなかったからッ!!」
青年は勢いに任せて子供を強く抱き締め、あの時は言葉にしなかった想いを吐露する。
幼子は超直感という異質なものと引き換えに、感情の機微に疎くなってしまったのか。
子供は知らず知らずの内に、自分に向けられた想いの裏を読むことができなくなっていたらしい。
だが、彼自身はそのことに気づいていなかった。
「……何が、違うの?」
「ツナく「どちらも同じ笑顔という産物なのに、何が違うの?」
こてんと首を傾げる子供に、青年は返す言葉を失った。
頭が真っ白になったと言っていいかもしれない。
少なくとも、昔の子供からは絶対に出てくるはずがない言葉だ。
違いなんて、彼自身が一番理解しているはずなのだから。
けれど、今の子供はそうではない。
自分の行為の不自然さに、何一つ……気づいていないのだ。
「エンマ君はさ、オレの本当の笑顔っていうのを知ってるんだよね」
「……」
「それってさ、何で“本当”ってわかるの? 痛みを隠して笑う方が“ホントウ”かもしれないのに」
可笑しな話だよね、と子供はぼやく。
それが当たり前だとでも言うように。
青年はひどくショックを受けながらも、骨が折れそうなほど強く子供を抱き締めた。
どうしたら彼の痛みに触れられるのか。
どうしたら彼の痛みを知ることができるのか。
そればかりを、ひたすら考えながら……。
【壊れた硝子細工、何が残るの?】
(君を変えたのは、僕?)
fin
- 13 -