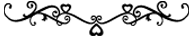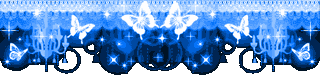

「……怪我、大丈夫ですか?」
「別に」
あれから男は、執務室に移動していた。
今はソファに座るのを拒否して、壁に寄り掛かっている状態だ。
隣の部屋で鈍い音がしたのを聞きつけたドン・ボンゴレが、慌てて様子を見に来たのだった。
男の拳からは血が流れており、顔色もひどく悪く見えた。
それでも男は群れを拒むため、自ら医務室には赴かないだろう。
ドン・ボンゴレは執務室に男を残すと、救急箱を取りに走り去ってしまった。
故に、彼は今此処にはいない。
代わりに男に声をかけたのは、先程まで彼と会話をしていたもう一人の……。
「雲雀さんでも虫が嫌いなんですね」
「悪い?」
「……いえ、意外だと思いまして」
もう一人のボス――古里炎真はソファに座りながら、重い沈黙を少しでも軽くするために苦笑した。
内心では、ドン・ボンゴレの一刻も早い帰還を心待ちにしながら。
もちろん泣く子も怯え逃げ出す雲雀恭弥が、非力な虫なんかに特別な感情を持つわけがない。
けれど炎真がそう言ったのには、明確な理由がある。
壁を殴った原因を聞かれた雲雀は、咄嗟に苦し紛れの言い訳を作ったのだ。
『蝿が飛んでたんだよ』
『『は?』』
『目障りだったから。結局逃げられたけど』
淡々と説明する雲雀に、絶対違うと二人共何故か確信できた。
何故か……というより、当たり前だろう。
この点を見れば、雲雀には僅かに天然要素があるのかもしれない。
だが二人共敢えて追及はせず、表面的には信じたフリをした。
優しさからなのか、咬み殺されたくないからなのか……理由は定かではない。
「そういえば、雲雀さん」
「何?」
話を振られて、雲雀は億劫そうにしながらも視線を合わせる。
炎真はいつのまにか雲雀の目の前に来ており、紅の眼差しが視界に映り込んだ。
敬語で話すところといい、雰囲気といい、何もかもが今は此処にいない人物に似過ぎている。
だから群れを嫌う自分が咬み殺さず、気紛れに許容しているのだろうか。
よくわからない、けれど嫌いではなかった。
無言で相手の話の続きを待っていると、炎真は申し訳なさそうな顔をして前置きをする。
「……僕の勘違いだったらすみません」
「だから何が「――どうしていつも、僕達のことを見てるんですか?」
予想もしなかった問い掛けに、雲雀の表情は冷静さを通り越して凍りついた。
治まっていたはずの胸が、またも激しく痛みを訴える。
油断をすれば声が出そうになったため、雲雀は咄嗟に唇を噛み締めた。
――殺された声は無音となり、誰にも届かず。
「――何が言いたいの?」
「いえ、その「はっきり言いなよ。回りくどいことは嫌いだ」
曖昧を一刀で切り捨てる雲雀に、炎真はばつが悪そうな顔をして俯いた。
やはり言うべきではなかっただろうか……。
今更後悔しても、時は既に遅し。
納得のいく説明をするまで、彼は自分を解放しないだろう。
炎真は己の浅慮を恨みながら、核心へと切り出していく。
「気配を消していたから最初はわかりませんでした。でも、たまに……感じるんです。雲雀さんの視線を。まるで強い感情に揺れてる感じで……その」
「ねえ、君。もっと簡潔に言ってくれない?」
雲雀は短気な性格そのままに急かす。
低く、脅すような声色で。
しかし、これ以上聞きたくないという思いもあった。
否、聞きたくないというよりは――聞いてはならない気がした。
もう二度と戻れないような、知らなかった頃には戻れないような……嫌な胸騒ぎ。
言い換えるならば、予感。
人間というものは、良い予感より悪い予感の方が当たりやすい。
ソレは――後者の方を無意識に強く思ってしまうからか。
未だに口を閉ざす炎真に、雲雀は余計腹が立っていた。
生殺しとも呼べばいいのか。
雲雀にとっては一番嫌いなパターンだ。
「あのさ、まさかこんな中途半端な答えで終わるつもりはないよね?」
唸るような声色で再度脅せば、炎真の小さな肩がビクッと震えた。
見るからに小動物、咬み殺す価値すらないソレ。
指輪に炎を灯した時だけ、別人のように雰囲気が変わるくせに。
その有り様は、どこまでもあの大空を思い起こさせる。まるで――そう。
「雲雀さんが見ているのは、僕達というよりツナ君で、だから……」
ようやく口を開いた炎真だったが、中々核心の核心を突いてくる様子はない。
途切れがちに落ちていく欠片は、雲雀の痛みをさらに増幅させた。
同時に、先程無理矢理思い起こされた記憶が、あの映像が声が脳内を侵食していく。
生き地獄か、まさに。
それでも雲雀は理性を保っていた。
無意識で知っていたのかもしれない。
ここで意識を明け渡したら、衝動に任せたら全ては終わりだと。
――ああ、それなのに。
「ずっと思ってたんです。雲雀さん、本当はツナ君のこと――がっ!!」
理性のタカが遂に外れてしまったのか。
我を忘れた雲雀は、勢い良くトンファーを振り下ろした。
一切の加減なく、何かに導かれるままに。
突然のことに受け身が取れず、炎真は頭部に直撃をくらって床に倒れる。
赤い髪をさらに染めるように、そこからは生命の色が流れ出していた。
「――」
何故人間とはこんなに脆い存在なのか。
命を奪われた亡骸を前にして、雲雀はひどく冷めた表情をしていた。
胸の痛みは跡形もなく消え去り、狂った高揚感だけが全身を支配する。
ああ、こんなにも簡単なことだった。
気づいてしまえば、実行に移すだけ。
何故こんな簡単なことを、自分は今まで為さずにいたのだろう。
笑いが込み上げて仕方がない。
――遠くから、誰かが走って来る足音が聞こえた。
真直ぐに、この部屋を目指す――足音、が。
もう少し早く来てくれていたなら……なんて、都合の良い望みでしかないのだ。
運命は、いつだって残酷なもの。
「雲雀さん、遅くなって――エンマ君ッ!?」
「やあ、綱吉」
横たわる炎真の元に駆け寄ろうとした沢田綱吉に、雲雀は優しく微笑みかける。
身体の芯から凍りつきそうな、未知なる畏怖を抱かせて。
沢田が思わず持っていた救急箱を落とすと、完全に閉まっていなかった蓋が開いて中身がばらまかれる。
ところが、それに視線を向けられないほど、琥珀の瞳は雲雀だけに集中していた。
彼が名を呼んだことさえ、狂気の表われに思えて。
「ひば「――やっと、この胸の痛みがなくなったよ」
心から解放されたように、雲雀は満ち足りた顔をしていた。
漂う雰囲気は、いつもより穏やかで柔らかい。
けれど、目は笑っていなかった。
そうして動作一つ一つが、狂いの対象となって沢田に向けられる。
恐ろしかった、逃げ出したかった。
続きを聞いてはならないと、沢田は本能で感じた。
それなのに、足が竦んで一歩も動けない。
「あ、なたが……どう、して――こんな」
「その答えは簡単だよ。だって僕は――」
――君のことを、愛してるみたい。
まだ完全に自覚しきっていないのか。
疑問系のように口にした雲雀は、どんな魔性よりも綺麗に綺麗に微笑んだ。
不安定な情を注がれた大空は、もはや慟哭すら許されず。
「あーあ、やっちゃいましたねぇ」
霧を纏った青年は、木の幹に背を預けながら執務室の窓を見上げた。
罪を犯した者にしかわからない独特な空気が、室内から外へと漏れている。
青年は口の端を吊り上げ、面白そうに笑いながら独り言を音にした。
「ジョットはコザァートを愛していた。これは事実。しかし――沢田綱吉が古里炎真を愛していたかどうかは本人にしかわからないですよねぇ」
まあ僕には関係ありませんけどと言の葉を遺し、青年は霧の中へと姿を消していく。
――彼の真意は、誰も知り得ないままに。
fin
- 39 -