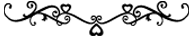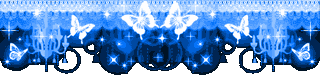

―――君が僕を殺したことで、僕の願いは叶えられたんだよ。
―――霧の守護者の名の下に、必ず彼を救いましょう。
嗚呼、僕等はなんて愚かで、取り返しのつかない過ちを犯したんだろう。
「報告書、確認してもらえる?」
任務から無事帰還した雲雀恭弥は、机の上に書類を無造作に放り投げる。
背もたれのある豪奢な椅子に座っていた沢田綱吉は、お帰りなさい、と笑ってそれを手にした。
一枚、一枚、丁寧な仕草で、不備が無いかを念入りに確認していく。
書類の量もあって結構な時間がかかったが、雲雀は何一つ文句を言わず、黙って待っていた。
「はい。確かに受理させて頂きます」
ドン・ボンゴレに相応しい威厳に満ちた声色は、敬語を使用していても威力を半減させなかった。
沢田は報告書を封筒に入れると、引き出しを開けてそれを片づける。
作業を終えて立ち上がれば戸棚を漁り、日本の有名ブランドであるお茶が入った缶を取り出した。
「雲雀さんの口に合うと思って、最近仕入れたんですよ。一杯どうです?」
「君が望むなら付き合うよ。貸して?」
「え、俺が作りますよ。昔よりは、多分上達したはずですし」
「そう。じゃあ、君に任せるよ」
雲雀は潔く引き下がり、ソファに座る。
沢田はお茶の缶を手にし、給湯室となっている奥の部屋へと消えて行った。
「ふふっ、今日は美味しいお茶を飲んでもらおうっと」
毎回、自分がやると意気込むまではいいのだが、お湯の温度を間違えたり、湯呑みを少し温めておくのを忘れてしまい、何か物足りない味となってしまう。
雲雀は最初こそ小言が多かったが、最近は諦めたのか何も言わなくなり、黙って飲み干すようになってしまった。
美味しいかと聞いても、普通としか返さないため、時折訪れる草壁に、味のチェックをしてもらっていた。
さすが補佐というだけあって、雲雀の好みを舌と鼻で把握しているらしい。
沢田にとっては、心強い味方だった。
「よし、今日は上手くいったはず!」
まるで新妻のような幸せオーラを漂わせながら、出来たお茶を、二人分の湯呑みに入れる。
小さなトレイにそれらを乗せれば、日本の商品を扱う店で購入した桜餅を二つ、青い縁取りがある皿に用意した。
こちらもお茶を購入した店で仕入れており、日本では名店の商品だ。
お茶と桜餅を用意出来たことに満足し、沢田はそれらを乗せたトレイを執務室へ運ぶ。
「雲雀さん、お待たせしま……ってええぇぇ―――っ! リボーン!?」
執務室に戻って来た沢田は、突然の来客に思わず手が滑りそうになった。
何とかそれを制し、雲雀の向かい側のソファに座っている大人の雰囲気が漂う男……リボーンを見据えて溜息を吐く。
「何でお前が此処にいるわけ?」
あからさまに不愉快さを前面に押し出し、無言で帰れと視線で促す。
しかし沢田がまだ未熟なせいか、リボーンには全く効果が見受けられない。
「フン、色惚けしてるボスに、オレ様が直々に喝を入れに来てやったんだ」
「ハァ? 誰も頼んでないんだけど」
「ダメツナが口答えすんじゃねえ。さっさとエスプレッソを用意しやがれ」
「はぁ……」
無茶苦茶な要求に深々と溜息をつき、小さく肩を竦めた沢田は、トレイをテーブルに置いた後、頬を掻きながら面倒そうに告げる。
「あのな、エスプレッソなんて給湯室にあるわけないだろ。キッチンまで行かなきゃ「オレを待たせたらどうなるか、わかってんだろーな?」
ジャキッと眉間に突きつけられた銃口に、怠惰の色を携えた沢田の表情は一転し、冷や汗をダラダラと流していた。
幸せな一時に意識を置いていただけあって、中々この現実に戻って来れない、
否、戻って来たくないのだろう。
助けを請うように視線を投げるが、雲雀は黙って静寂を保つ。
微笑むことすらなく、機械に近い無表情の様には、何かを思い起こされた気がして、沢田は泣き出してしまいそうだった。
リボーンは二人の様子を訝しく思い、立ち上がると扉を開く。
帰ってくれるのかと期待した沢田は、オブラートに包むことなく、疑問を率直に口にした。
「諦めてくれた?」
「辛気臭い顔してんじゃねーぞ。ダメツナが」
リボーンは沢田の背後に回り、勝手に安堵している態度を粉砕するかの如く、思い切り背中を蹴り飛ばした。
「いってえっ!!」
どれだけの力が加わったのだろうか。
沢田は廊下にまで飛ばされ、顔面を床に打ちつけるようにして倒れた。
文句を言おうと振り向いた瞬間に、無情にも扉は堅く閉ざされ、鍵まで掛けられてしまう。
エスプレッソを持って来たら開けてやる、と内側から声が聞こえれば、沢田は恨めしさを抱きつつも立ち上がって、とぼとぼと歩き出した。
何で俺が、とぼやいていたが、心は、ひどく、重い。
「行ったな……」
「そうみたいだね」
言葉に感情は無く、台詞とは呼べない、それは空気を震わせる音。
リボーンはそれに敢えて触れず、揶揄めいた口調で、試すように言葉を発した。
「ヒバリ、アイツをあまり甘やかすな」
「何のこと?」
「お前達を認めてないわけじゃねえ。だが、最近のお前はアイツに甘すぎる。少しは厳しく接してやってもいいんじゃねーか?」
「僕は、彼の望みを聞いているだけだよ」
「フン、それがおかしいんだぞ」
ピシャリとリボーンは言い放つ。雲雀は首を傾げたが、顕著な動揺を見せることはなかった。
否、心が動いている感じがしてこないのだ。
余程訓練を積まなければ、さざ波一つ立てずに、心の平穏を保つことはできない。
数ヵ月前は、こんな変化を見られなかった。
だから、何かがある、と確信したのだ。
けれど、それが開けてはならないパンドラの箱だとは、思いも寄らないで。
「数ヵ月前のお前はまだ、ツナと一定の距離を保っていたはずだ。少なくとも、ツナの提案を鵜呑みにしたりしねえ。それに、群れを咬み殺さなくなったな。会合にも参加するようになったし、明らかに此処で過ごす時間が増えてる。しかもツナとの時間を邪魔する奴は、オレですら咬み殺そうとしたお前が―――どういう心境の変化だ?」
「……さあ、ね。そんな話をするために、彼を追い出したの?」
雲雀が向けたのは相変わらず、思考の読み取れない曖昧さを帯びた眼差し。
リボーンはそれに益々疑問を深め、眉間に皺を寄せていく。
「―――不服か?」
「僕には関係ないよ。君の好きにすればいい」
雲雀らしい、己の他は一切の拒絶。
しかしそれすら、リボーンには意味が違って読み取れた。
関係ない、それは嘘、数ヵ月ならば。
関係ない、それは真実、今現在は。
「ヒバリ……」
これ以上は無駄だと悟ったリボーンは、口を閉ざして目を瞑る。
耳を済ませれば、扉の外側から、ドタバタと忙しない足音が聞こえてきた。
エスプレッソを手にした教え子だろう―――約束通り鍵を開けてやれば、勢い良く扉が開いて沢田が飛び込んで来る。
「がはっ!」
同時に空間に飛び散ったのは、きれいな、きれいな、あかい、いろ。
飛散してはならない、いのちの、いろ。
「ヒバリ!?」
「雲雀さんっ!!」
急に吐血した雲雀を見た瞬間、沢田はリボーンを押し退け慌てて駆け寄る。
リボーンは医療斑を呼ぼうとしたが、スーツのポケットに入れていた携帯の着信音が鳴れば、チッと舌打ちをして通話ボタンを押す。
「―――ああ、オレだ。なんだ、と。任務中の六道骸が重傷を負った!?」
「っ! どこっ、骸はどこにいるのっ!!」
先程まで雲雀の心配をしていたはずなのに、今の沢田はリボーンから携帯を奪って、骸が運ばれた病院の場所を聞き出していた。
血相を変え、声を震わせ、両手にびっしょりと汗を握る沢田の姿に、リボーンは一抹の不安を覚えてしまう。
「おい、ツナ「病院に行って来る! 雲雀さんは仮眠室に寝かせて。間違っても、絶対医療斑に診せないで!!」
最後だけ強く念を押すように言い残し、沢田は超モードで窓から庭へと飛び降りた。
炎の推進力を最大限利用すれば、一気に空中を移動する。
「一体、どういうことだ。何でヒバリが血を吐いた同時刻、骸が重傷を負ってやがる。それに、ツナのあの反応は……」
更に疑問が積み重なったが、真相への糸口は見え始めてきた。
リボーンは部下に連絡すると、雲雀を仮眠室に運ばせ、自分は真実を秘めた病院へと車で向かう。
―――パンドラの箱に手を掛けた先、待ち受けるのは悪魔か堕天使か。
- 2 -