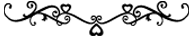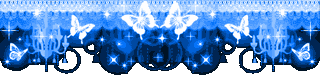

「ヒバリさん、必ず幸せにしますね!」
ある日の、並中の応接室だったか。僕より年下の小動物は、それはそれは柔らかい微笑みを浮かべて、僕を抱きしめてきた。背が小さくて、華奢で、悪く言えば頼りない貧弱。どちらかといえば、彼の台詞は、僕が言う台詞じゃないだろうかとさえ思った。でも、彼が、彼が、あまりにも幸せそうに微笑んだから、僕は柄にもなく頷いたんだ―――。
「―――ホント、不愉快な夢だ」
ぽつりと呟き、布団から起き上がった雲雀恭弥は天井を見上げた。立ち上がろうとしたが、腰に尋常でない痛みが走り、思わず苦痛の声を漏らす。
ふと隣りを見れば、昨夜情事に及んだ相手は既に姿を消していた。自分はよほど深く眠っていたのだろう。相手が出て行ったことに、微塵も気づかないだなんて―――そう思っても、雲雀は自分から認めようとはしなかった。たまたま、だと……もう、ずっと、ずっと、昔から、そう思い込んでいるのだ。
「昨日が、最後だったのにね」
名残惜し気に、忌々し気に、言葉を発する。
俺、結婚するんです……と言った彼は、とても幸せそうな表情で満ち足りていたんだっけと考えながら。けれどそれを聞かされた時の自分は、世界が崩壊して、目の前が真っ暗になる感覚があった。
「必ず幸せに……なんて、嘘を吐いて」
気を許したことが間違いだったかと、胸元に刻まれた紅い所有印に触れながら後悔を馳せ、少し乱れていた着物を整えた。彼が眠っていた位置に触れれば、まだ生暖かい感触が指先を通して伝わってくる。時間の許すギリギリまで傍に居てくれたのか……なんて、残酷な優しさを遺していくのだろう。
ふと名も知らぬ感情に駆られ、雲雀は指先をすーっと滑らせた。動きはある一点で止まり、丸くて小さな染みを見つけると、快楽の行為が心に蘇ってくる。自然と口元を綻ばせ、染みに触れた指先を舐めれば、予想外の塩っぱさに眉を顰めた。
「……なみ、だ?」
思わず口をついで出た言葉に、小さく嘲る。気のせいかもしれない。大体、布団に溶け込んだ液体の味なんて―――普通判別できるはずがない。
彼が泣いてくれていたら、結婚は彼の意思ではなかったんだとしたら……そんな、少女のように淡い希望を、自分は抱いているのか。らしくない女々しさに、雲雀は舌打ちをして、再度布団に横になった。
枕元の近くに置いておいた携帯電話を開けば、時刻は午前五時を示している。普段なら起床の時間だ、とぼんやり考えたが、昨夜の件で身体が怠くて思うように動かない。昨日は随分激しく抱かれたんだったか。まるで、別れを惜しむように―――そんな思考が一瞬頭を過ると、首を軽く振って即座に追い払った。
「馬鹿馬鹿しい。彼は笑っていたんだ。俺なんかの妻になりたいっていう女性がいるんですよ。物好きですよねって……馬鹿げてる。彼にとって、僕はただの遊びだったんだ……」
そんな素振りは全く見せなかったから、不覚にも安心しきっていた―――それだけのこと。
髪を撫でて、額に、唇に、そっと口づけ、貴方を一番愛しています……なんて、いとおしそうに告げるから、愚かにも信じてしまっただけのこと。
瞼を閉じたが眠る気になれず、仕方なく起き上がると布団を払い退けた。瞬間、布団から畳へと、何かがころころと転がっていく。
雲雀は不審な音を聞いて訝しく思い、立ち上がるとそれを拾い上げた。手の平の中で、穢れ一つ無い漆黒の携帯電話が、鈍く光る。
雲雀は咄嗟に枕元を見たが、自分の真紅の携帯電話は其処に置かれていた。
漆黒と真紅、互いに想いを交わした証。雲雀は漆黒のそれを握り締め、はらはらと涙を流す。
真紅は……精一杯の譲歩だった。本当は橙色が、彼の灯す気高い炎の色が良かったのだけれど、それを具現化できる技術は、まだ発達していなくて。いや、どんなに年数を経ても、あの神々しい色は出せないだろう。神など元から信じていない自分が、あの炎を見る時だけは―――ちっぽけな考えを、改めていたのだから。
「わざと忘れたのか、それとも……そそっかしいだけなのか」
どちらとも取れる状況だったが、面倒事を嫌う雲雀は、握り締めた携帯をごみ箱の中へと落とした。ガチャンッという音が中で響き渡り、何かが壊れる小さな音が耳を通過する。
もう使い物にならないだろう。もし彼が戻って来たとしても、絶対に謝ってやるものか。
そう、そう思っていた。これからも、そう思い続けられたら―――きっと、雲雀は“とても”幸せだったかもしれない。
何かを予感したのか、雲雀はふっと自分の携帯へと視線を逸らした。同時に鳴り響くのは、指定した覚えのない着信音。
真紅の携帯が奏でるそれに、何とも言えない複雑さを抱いた。早く、早く、彼の色を処分してしまわなければ―――心は、魂は、そう叫んでいるのに、足は何かに操られるかのように歩を進め、伸ばされた手が携帯を拾い上げる。
指先が触れるのは、深淵を約束する受話ボタン。
「……もしもし」
「雲雀、ですか?」
「六道?」
電話の向こうから、躊躇いがちに聞こえてきた声に、雲雀は少しだけ安堵する。それを感じながら、自分はどうしても、彼に会いたくないのだと思い知らされた。
「どうかしたの?」
努めて冷静に、普段通りを装うが、六道骸の方は違っていた。人を小馬鹿にする冗舌さは全く感じられず、逆にどうすればいいのかと言葉を吟味しているようだ。
慎重と緊張、厳粛な空気が一気に伝わり、雲雀は自然と喉に渇きを覚える。あれだけ喘がされれば喉が渇くのは当たり前だが、これは何かが違う。
けれど、言葉では表現できぬ違和感の正体は、骸の告げた台詞で全てわかった。
「―――訃報です。我等がボス、沢田綱吉が……婚約者に殺されました」
「―――っ!!」
目の前が真っ暗になる……なんて、生温い表現では語れない。身体の血を全て抜かれ、取り出された心臓が串刺しで焼き尽くされ、一縷の望みさえ根こそぎ奪われたような……叫ぶことさえ許されぬ絶望だった。
「彼の婚約者は、恋人を殺された復讐だと言っていました。ドン・ボンゴレさえいなければ、彼と結婚できた。彼は自分の父親に殺されなくて済んだ……と」
完全な逆恨みの文句も、雲雀の耳には聞こえてこなかった。
彼が、沢田綱吉が、死んだ?ボンゴレを護ると誓った彼が、殺意に溺れた狂女の手で殺された?
なんて、なんて、タチの悪い冗談なんだろう。先程まで流れていた雫もいつしか止まり、ひやりとした頬だけが己を戒める。それでも足りないというのか、唇から紡がれる真実は、まだ終わらない。
「……許しがたいのは、彼が彼女の復讐を受け入れたことです。彼は今朝早く、彼女と会うためにホテルを一室借りています。事件は……其処で起きました。僕がもう少し早く辿り着けば、あの程度の幻術など見破れたでしょう。しかし、霧の匣でカムフラージュしてあった室内は、一見何の変哲もない部屋に見えるため発見が遅れ「そう、死んだの」
自分でも驚くほどの冷めた声を、雲雀は淡々と零した。哀れみに近い声色で、雲雀君と言い掛けていた骸を無視し、電話を切れば電源を落とす。
静寂を取り戻した室内で、雲雀は先程のごみ箱から漆黒の携帯を抜き、震える指で折畳みを開く。
視界に飛び込んできた待受画面は、一枚の写真のようだった。ソファに寄り掛かって眠る雲雀の頬に、横からそっと口づける沢田の姿は、恐らく画像処理したものだろう。執務室で沢田を待ち疲れた時、不覚にも眠ってしまった時が何度かあった。その中の一つ、なのだと雲雀は推測する。
実際に撮った姿ではないのに、画面の中で幸せそうに微笑む沢田を見ていると、苦しさで胸がはち切れそうになった。
「っ……なんで、なんで君は、こんなものを―――ッ!!」
前言撤回だ。残酷な優しさなんて、彼にはない。狡いだけだ、卑怯なだけだ、死んでも僕を縛り続けるだけじゃないかっ!
治まったと思った透明な水が、再び目尻から零れて頬を伝う。どんなに泣き叫んでも、どんなに罵っても、柔らかな大空は、二度と、この手の中に、戻ることはない―――。
「ヒバリさん、必ず幸せにしますね!」
約束したんですよ、俺。
護るつもりだったんですよ、絶対。
それなのに、彼女の怨みを聞いたら、できなかったんです。
彼女と恋人の立場を、俺と雲雀さんだったらって、そう考えたら―――できなかったんです。
ふふっ、死んでも俺は我儘ですね。
貴方を愛してるから、誰にも渡したくないんです。
ねえ、俺の色を忘れないでくださいね。
fin
- 2 -