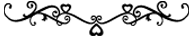何がしたいのだろうこの子供は。
最初に抱いた疑問はそれだった。
指輪の思念体に拘束など無意味だ。
己の両手首にはめられた手錠に溜息を吐きながら、伸し圧かっている子供を見上げる。
両手は頭上で固定され、彼の片手は握り締めるように手錠を掴んでいる。
何重にも拘束をしたところで状況は変わらないのに熱心なものだ。
まさかソファーに押し倒されるとは思わなかった。
戦う気はないみたいなのが幸いか。
手を貸せと、言われるままに差し出したのは迂闊だった。
正直、彼が何をしようと別に驚きはしない。
唐突な行動はこの子供の専売特許だ。
雲の守護者を継ぐのだからこれぐらいは然るべきだ。
先を読まれるようでは器が知れる。
「重いんだけど」
「どうせ感じてないでしょ」
心なしか拗ねているようにも思えた。
年相応の子供といえば子供。
戦闘意欲だけは異常、悪い言い方をすればそれ以外に興味を持たない。
昔の自分を少しだけ思い出して、重ねたことに内心辟易する。
恐らく、恐らく、だ。
彼と僕が反対の立場だとしたら、やはり欠片ほどは執着したかもしれない。
根拠はない。
ただの推測。
そんなことをするほど、この子供の存在は無視できないほどになり始めている。
同じ雲というだけで?
顔が、性質が、似ているというだけで?
様々な考えが浮かんでも、変化の決定打は浮かばなかった。
「何考えてるの?」
「別に。君には関係ないよ」
「またそうやって。だからあなたは嫌いだ」
「嫌い? ならこれは嫌がらせかい?」
馬鹿にしたようにふっと笑えば、頬を叩かれる。
手首のしなり方からして、相当の力が入っていたことは伺えた。
利き手ではないだろうに無駄な力だけは馬鹿みたいにある。
生憎この身は生身ではないから、強さを測ることはできなかった。
もしかしたら、痛みを感じるよう感覚を生かすこともできるかもしれない。
けれどそれは滑稽だ。
自分が死人だということを忘れそうになる。
百年前に、己はとっくに生を終えているのだ。
会話を交わせても、生前のように自由に身体は動いても、同じではない。
いつかは消える。
それがいつなのかは僕にも解らない。
あってはならなかったことだけは、確か。
「痛い」
「よく言うよ。何も感じてないくせに」
「そうだね。もう死んでるから」
子供の顔が泣きそうなぐらい歪む。
今の言葉のどこにそんな表情をさせる要素があったろう。
意外に感情表現が豊かだと気づいたのは、いつ頃だったか。
最初は戦闘狂の無口で無愛想な子供と認識していた。
獲物を前にした時だけ、口元を綻ばせて凶器を奮う。
けれどよく観察すると、様々なところに変化が見られるのだ。
中でも、彼の飼っている小鳥の前では幾分表情が穏やかだ。
歳相応に笑えるのかと新たな一面を見た気がする。
思考に耽っていれば、彼の指先が喉元に触れた。
感触はないけれど、冷たいのだろうなと何となく思った。
温かかったら意外だ。
どちらにせよ、感覚を開かなければ確かめようがない。
でも、わざわざそうする価値を見出だせない。
無駄なことはしない主義だ。
死んでまで振り回されているのだから、せめて己の意思ぐらいは通したい。
譲歩という面が見えることに自嘲した。
いつの間にか容する範囲が広がっていたと。
だが興味があるかどうかはまた話が別だ。
指先がゆっくりと拙い動きで首筋をなぞり上げる。
生身なら、少しは震えただろうか。
「さっきから何がしたいの、君」
「……あなた、何にも興味がないなんて、嘘……でしょ」
随分唐突だ。
やはりこの子供の思考回路は理解し難い。
戦闘だけを望んでいるのなら、こんな回りくどいことをする必要などない。
興味を持たれたいのか、つまりは。
興味を持つことが戦闘に繋がるとでも?
単純な自己完結思考回路には恐れ入る。
「あなたは……プリーモって人が好きなんだろ」
「……は?」
予想外の予想外に、自分らしくない腑抜けた声が唇から洩れた。
聴覚の不調か。
幻聴なんて、生前ですら聞こえたことがなかったのに。
けれど、詰め寄ってくる子供の表情は真剣そのもの。
「はぐらかす気? あなたを見ていれば解るよ。プリーモって呼ぶ度に、優しそうな眼差しをしてさ」
「……嗚呼、僕は君のものじゃないけど、君は嫉妬してるのか」
「っ……そういう態度がムカつくって何度も言ってるよね」
睨みつけてくる灰の瞳は鋭さを増していた。
仕方ないじゃないか。
これ以外に何を言えと言うのだ。
寧ろ彼の自業自得だ。
根本からズレてる相手に諭すよりは、肯定して有耶無耶にしてしまった方が早い。
本心も誤解も悟らせない。
ただ受けて、そのまま言葉を吐く。
大切な仕事ならいい加減なことはしないが、この子供相手なら充分譲歩しているはずだ。
「君が苛立ったところで僕には関係ないな」
「だから嫌い」
「そう。僕はどちらでもないよ。最初から“興味はない”からね」
「……っ」
眼中にないことに苛立ったのか、唇を噛み締めて未だに睨みつけている。
彼の指先に、力が加わった気がした。
気道を圧迫され、僅かな苦しさが襲う。
酔狂だ。
実際には解らない、はずなのに。
「……そうだね。あなたは僕なんてどうでもいい」
「何を今更。理解したなら外しなよ。茶番には付き合ってあげただろ」
敢えて上から目線で言ってやっても、彼は無言で伸し圧かったままだ。
本当に子供だと思う。
都合が悪くなれば口を閉ざし、無言を貫く。
意味を成すなら、暴力という手段も厭わなかったろう。
雲の守護者が掲げる孤高には程遠い。
「別に嫉妬なんかしてない。勘違いしないで」
付け足されたような台詞も、空振りの虚勢にしか見えなかった。
否定するのが遅過ぎることに、きっと彼は気づいていない。
ムカつく、も、嫌い、も、的を射たからこそ出る言葉だと。
図星だと認めているのに、本人の顕在意識は認めていない。
厄介だ。
無自覚の愚かさは身を蝕むだけ。
自覚できなければ堕ちるだけだ、無様に。
「まあ、どうでもいいか」
「嘘吐き。あなたは彼が「いつか消えるモノに執着するなんて、僕には解らないしね」
思ったままを突きつけた瞬間、互いに纏わりつく空気が凍る。
ガチャリと外れた手錠が床に落ち、無機質な音を立てる。
灰の瞳から零れた一粒の涙は、僕の瞳に落ちて滲み融けていった。
【涙叫鉄触〜ルイキョウテッショク〜】
(報われるとか、叶うとか、そんな安っぽい想いじゃなくて。……例え、冷たいだけだとしても)
fin
- 1 -