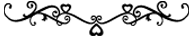「恭弥、何を読んでるんですか?」
和室の襖に背を預けて座る恭弥に、本から目を上げて訊ねる。
僕が読んでいた本はひどく退屈な恋愛小説だった。
クロームに薦められたから仕方なしに読んだが、そうでなければ一ページで投げ捨てている。
彼の私邸を訪れた時は生憎仕事中だったため、終わるまでの時間潰しには役立ってくれたか。
まあ明らかに仕事をしている風には見えなかったけれど、彼だから仕方ない。
いつも勝手に来るなと言っても、結局は同じ空間を共有してくれるわけで文句があるはずもない。
十年という月日は人を変えるに充分だったのだろう。
とりあえず、出会い頭に言葉もなくトンファーを奮われることはなくなった。
十年前は幻覚の姿にさえも迷わず攻撃してきたのだから確実な進歩だ。
「恭弥?」
もう一度呼び掛ける。
一旦集中するとどんな雑音も耳には入らない。
解ってはいたが、彼がたった一枚の紙を眺めたまま三時間は経過している。
何か仕事の資料だろうと思ったが、一分もかからず読み終えて頭に入れてしまう彼だ。
可能性は限りなく低い。
「恭弥」
だんだん声に苛立ちが伴ってきた。
立ち上がっても、彼が気づいた様子はない。
ただ紙を追ったまま、一瞬たりとも逸らすことはなかった。
眼差しは真剣で、周りなど眼中にない。
自分一人だけの世界に没頭している。
勝手に押し掛けてきたのは悪いと思うが、この仕打ちはないと思った。
……けれど、その瞳が異常に充血しているのを見て些末な思考が払われる。
「さっきから何してるんですか君は」
紙を掴んでいた力は緩かったのだろう。
近づいて容易く奪えば、真っ赤な目をした恭弥と視線が合った。
瞬きをした彼の瞳から、幾粒もの涙が零れていく。
何度か繰り返しているのは、それまで全くしていなかったからだろう。
三時間ずっと、この紙を凝視していたのだ。
ひどく乾く眼球に構うことなく、ひたすら。
何をしても泣くことがない彼の泣き顔は、貴重だと思う。
少なくとも、自分は見ることがないと思っていた。
だからこんな簡単に目にできたことに驚きを隠せない。
或いは……いや、まさか紙面の内容に泣いたわけじゃないだろう。
それこそ天変地異の前触れだ。
雲雀恭弥を泣かせるほどの内容なんて、世界中何処を探してもお目にかかれない。
「まだいたの?」
「君の仕事が終わるまで静かに待とうと思ったんですがね」
暗に興味がなかった的反応には突っ込まない。
これが日常だ。
彼は頑なに拒絶しない代わり、儘に振る舞う。
誰が何処にいようと、自分の邪魔にさえならなければ放置するのだ。
勿論例外もあるだろうが、大半は彼の気分の下で決まる。
「仕事……?」
「君が言ったんでしょう。仕事があるから用があるなら待てと」
「……ああ、うん」
絶対に憶えていない。
曖昧な返答は、それを証明していた。
始めに応対した時のことを思い返せば、適当にあしらわれていたような気がする。
大体この紙に何が書いてあるというのだ。
彼から紙面へと視線を移動させる。
抗議の声は上がらない。
他人に読ませても平気な内容なのか。
そんな疑問は、僕ですら読むことができない異国の文字を目にした瞬間払拭された。
イタリア語に似ている気もしたが、何か違う。
「君には読めないよ」
「そうですね。何処の国の言葉です?」
「さあ?」
クスクスと笑う様は完全に愉しんでいる。
涙はもう止まっていた。
君に解るわけがないだろうと、確信に満ちている雰囲気さえ醸し出している。
少しばかり対抗心を燃やして、今まで得た知識をフル回転させてみた。
けれどどれだけ記憶を辿っても憶えがない。
イタリア語のように見えるが、所々知らない単語が混ざる。
仕事柄各国の言語修得は欠かさなかったのに、この紙の解読には至らない。
彼は僕から紙を奪うことなく、手だけを差し出す。
返して、と小さく声が発された。
無理矢理奪い返さないところから、そうしたくないことが伺い知れた。
そんなに大切なものなのか。
……醜悪な感情が、芽を出す。
「欲しければ奪えばいいでしょう?」
「そんなことしたら破けるだろ」
「おや、僕を放っておくほど、破りたくないほど、これが大切ですか?」
嘲って意地悪な質問を投げれば、恭弥の瞳が鋭く光る。
目は口ほどに物を語るとはよく言ったものだ。
幾千幾万の罵倒より、彼の睨みつけるという行為には数多を震えさせ屈させる力がある。
「これが何なのか教えて頂けませんか?」
「君には関係ないだろ」
「紙吹雪にして差し上げましょうか?」
「……手紙だよ」
脅し混じりに聞き出した答えは、無駄な装飾のないシンプルなもの。
仕事絡みではない、手紙。
となれば、私物か。
……何故か、胸の中に重いものが溜まっていく気がした。
「誰からです?」
「故人だよ」
淡々と質問に答える彼は、決して間違いではない。
でも僕が知りたい答えではないのも事実。
畳み掛けるように質問をすれば、彼は一言二言で返してくるだろう。
不機嫌度を最高に募らせて。
そこまでして聞き出す必要があるだろうか。
彼だって手紙のやり取りをする相手ぐらいはいるだろう。
元々和を好む彼だ。
風情のない電子メールより、趣深い直筆を楽しんでいてもおかしくはない。
それなのに、胸の奧がざわついてざわついて仕方がなかった。
瞬きさえ忘れるほど、涙を流すほど、だからか。
恭弥の肩を空いている手で掴み、声色を強める。
「誰ですか?」
「君、どれだけ人のプライバシーを侵害するつもり?」
「いいから答えなさい」
彼の表情が、不快に歪んだ。
眉間に刻まれた皺は、常の苛立ちからよりも深い。
命令口調を好まないことは知っている。
本当に聞き出したかったら、これは最悪の手だ。
機嫌を損ねるだけで、無駄に怒りを買うだけで意味がない。
「……そんなに知りたいわけ? 嗚呼そっか。この手紙の主と恋仲だとでも思った?」
「っ!?」
原因を突かれて、動揺が走る。
知らずに肩を掴む手に更に力を加えていた。
顕著に見えたであろう変化に、彼はまたクスクスと笑う。
無駄な色香を漂わせて僕の頬に触れるのは、指先でなぞるのは、故意犯だろう性悪な。
「残念ながら彼とはそんな関係じゃないよ。でも……一つだけ教えてあげる。エビングハウスの忘却曲線、って知ってるかい?」
「……ええ。読んだものは読み終えた直後の忘却速度が速い。約一日で半分以上頭から抜けてしまう、という法則でしょう。それとこれに何の関係があるんです?」
声は荒々しく刺々しくなる一方だった。
ようは復習が大切だという、学習に於ける単純な法則だ。
しかしどう頭を捻っても、手紙とは結びつかない。
彼にとって内容の記憶ぐらい朝飯前だろう。
一枚の紙に、記憶の保持が不可能なほど膨大な情報量が含まれているとは思えない。
ましてや、三時間瞬きなしで読み続ける必要があるとは到底思えない。
「内容だけなら、確かに簡単だね」
僕の疑問を察したのか、彼が呟く。
相変わらずの頭の良さだ。
直感と呼ぶには野性が勝ち過ぎていることは否めないが。
「僕が憶えていたいのは内容だけじゃない。その手紙の感触や状態、書かれた文字の一字一句、その癖から文字の間隔に至るまで、何もかも全く同じように記憶したいのさ」
「……」
辿り着けなかった思考に絶句する。
不可能だ、そんなこと。
同時にそうまでして彼を駆り立てる代物を、今すぐ八つ裂きにしたい衝動に苛まれた。
【エビングハウスの忘却曲線】
(憧れていたんだ、あの人に。恋とは違うけど、焦がれてた)
fin
- 2 -