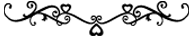ぷかぷかと、広めの水槽の中でたゆたう状態が心地好かった。
現実より重力を手放しているせいか、解放感も高まっている気がする。
水槽をイメージしたのは、昔囚われていた感覚が懐かしくなったから、だろうか。
夢、精神世界でまで囚人を装うなんて馬鹿げている。
囚われたいのか、僕は。
上に向かって片手を伸ばしてみる。
掴めるのは程良く冷たい水の感触だけだ。
他には何もない。
当たり前だ。
この水槽の中には僕しかいない。
服を着たままでも気にならないのは、やはり夢だからか。
今の状態に鎖でもあれば、見事に昔の再現だ。
育てのファミリーを屠り、マフィアも一般人も見境無く手にかけてきた。
故の、水牢。
アレは罪を悔い改めろなどという生易しいモノではない。
永遠に縛る、枷だ。
死を以て外されたと思っても、繰り返す輪廻にまた縛られる。
何度かアレに囚われたことがある気がしていることも関係しているのか。
絶対不可侵の領域、に。
「――何してるの」
外側から、興味のなさげな淡々とした声が響いた。
水槽を形作る硝子は、音を遮断することはないらしい。
敢えて視線を向けることなく、そのまま浮遊を享受する。
相手の姿など見るまでもない。
彼はいつも不意に現れ、そうして去っていく。
僕も同じことをしているから人のことは言えないのだけども。
――しかし、他人の夢の世界に介入するのは容易くない。
現実にある身体が別々の場所にあれば尚更だ。
記憶によれば、一度は夢への介入の仕方を彼に教えた。
成し得るとは思ってもみなかったけれど。
尤も、遣り方自体はそう難しくはない。
夢の波長と条件さえ合えばいいのだから。
僕と彼の波長はそう悪くはなかったし、月日が経つ毎に合う部分が増えてきていた。
ならば後は条件のみ。
ソレこそが問題だと思っていたのは、どうやら僕の勘違いだったらしい。
彼にとっては何ら障害にもならなかったようだ。
「……此処を訪れるほど僕のことを想っていてくれたんですか?」
「否定しても信じないでしょ。それより水の中で話せるなんて器用だね」
「夢の中ですから」
皮肉を軽く流す。
会えば厭味的な会話から始まるのは、もう日常茶飯事だ。
それでも昔のように過剰に反応し、凶器を奮うことはなくなったのだから進歩したと言えるだろう。
正直、あの性格は一生変わるまいと思っていた。
老いて丸くなる、なんて論外とも。
自分は意外に思い込みが激しかったようだ。
彼に関して、絶対の部分が多すぎる。
否、変わらないでいてほしいと、無意識に願っていたのかもしれない。
長いこと向けられた執着と凶器と殺意を、たまに懐かしく感じてしまう。
心身が馴らされたのだとしたら、迷惑極まりないことだけれど。
「――ねえ、」
「はい?」
ふと、視線を下げて彼の方を見た。
真剣な面持ちで、水槽に触れている。
硝子を指先でなぞり、質感を確かめる仕草にも似て。
……何故だろうか。
黒曜石の瞳が、睨んでいるように見えるのは。
「君はずっと、こうやって冷たい水の中にいたの?」
「……ええ。此処よりは狭く窮屈でしたよ。鎖に繋がれていましたしね」
「……」
彼は口を閉ざして黙ってしまった。
答え方としては別に間違っていなかったと思う。
それでなくても彼の場合、何を指しているか明確でないことが多々なのだ。
だが詳細を問えば、面倒だと言わんばかりに背を向けてしまう。
何とも自己中横暴理不尽。
そう非難することもできたが、結局自分は苦笑しつつ受け入れてしまう。
大概甘い。
「……そう」
やっと口を開いたかと思えば、たった一言。
裏腹に、脳内では様々な思考が駆け巡っているのは察せた。
それらを要約したのがこれだとしたら、彼の言葉少なさは考え過ぎにあるのではないか。
指摘したところで、一蹴されるのは目に見えているが。
「……」
何か言いたげに唇を開くが、閉じる。
さっきからそんなことの繰り返しだ。
他の煮え切らない態度にはっきりしろと咬み殺すくせに、彼自身もまた同じことをしているのだから呆れてしまう。
いい加減視線だけ下げているのも疲れてきた。
これ以上の休息は望めなさそうだ。
(いつもの状態に戻しますかね……)
視線を目の前に戻し、瞼を閉じた。
景色を変えようと、精神を集中させる。
――その時だった。
バシャンッと派手な水音が頭上で立ち、確認する間もなく何かに唇を塞がれる。
頬に添えられた柔らかい感触に、手の平だということだけは何となく解った。
ゆっくりと目を開ければ、外側にいたはずの彼の顔が視界を覆っている。
……キスされているのだと、頭では理解した。
不意打ちは隙を産み、僅かに開けてしまった唇から彼の舌が入り込む。
その先の展開は何となく予想がついたが、何もこんな所でやらなくたっていいじゃないか。
付け加えるなら、夢だからといって人間離れした瞬間移動やら跳躍は止めてほしい。
どちらだろうと現実には到底成せないことだ。
否、彼ならばやりかねないのが怖い。
口内を泳ぐ舌の動きが、含んでしまった水を掻き回して息苦しい。
現実世界ならば死ぬ気で抵抗しただろう。
こんな死に方は御免だ。
恥曝しでしかない。自由に泳ぎ回るソレは、未だ僕の予想に収まりはしなかった。
焦らしているのだ。
或いは、僕から動くのを待っているのか。
思惑に乗るのも癪で、ただひたすら彼が痺れを切らすのを待つ。
生き物のように動き回る度、唾液が混ざった水を強制的に飲み干して気持ち悪くなった。
夢とはいえ、此処も一つの世界。
起きていることは決して夢ではない。
下手をすれば、現実以上か。
魂に直に触れられているようなものだから。
……徐々に身体が熱くなっていくのを感じ、最早内心嘲ることしかできない。
痺れを切らしたのは僕じゃないか情けない。
動き回る彼の舌を絡め取り、両腕を背に回す。
一瞬驚いたみたいだが、黒曜石に昏い欲が孕んだのを見逃しはしなかった。
息さえ忘れるほど、互いに貪り合う。
まるで心中を望んでいるみたいだ。
小さな泡が幾つも立ち上り、酸素が溶けていく。
このまま死んでも可笑しくないぐらい頭がくらくらしていた。
充分に堪能したのか、彼はするりと舌を抜いて唇を離す。
銀糸が互いを繋ぐことはなかったが、ちりちりとした微弱な熱が心身を侵食していた。
「ふと、思ったんだ」
彼は呟く。
僕の頬に手を添えたまま、少しだけ枯れた声を響かせて。
「この水の、一粒、一粒が、君を縛る感情だとしたら……って」
「は……?」
真摯に語る彼には悪いが、間の抜けた声しか僕は出せなかった。
内容が内容なだけに、彼――雲雀恭弥から出たモノとは到底思えなかったからだ。
彼は根っからの現実主義者ではなかったか。
己が興味と戦闘以外はくだらないと切り捨てる、傲慢な排他主義者。
その彼が、水を、感情に喩える?
まるで詩人のやることだ。
ロマン主義だ。
あまりにも不似合い過ぎるだろう。
「君らしくもない。それにさっきの「――君を縛り捕えるのは僕だけでいい。……全部真っ黒に沈めてやりたいよ」
囁かれた言葉に、再び重ねられた唇に、僕は何も返すことができなかった。
もうとっくに喪われたと思っていたものを、垣間見てしまったのだから。
【空前絶後の恋情】
(こんなにも溺れたのは、たった一人だけだった。変わることなど、永遠に――)
fin
- 7 -