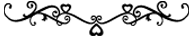インスパイア→ALI PROJECT 『灰桜』
創作BGM→妖精帝國『filament』
★★★★★★★★★★★
――暗い路地裏を、場違いなぐらいしっかり着熟したスーツで歩いていた。
月明かりも電灯もない、真っ暗な闇。
先程まで降っていた小雨は止み、冷やされた空気だけが残留している。
宛てもなく歩き続けることに意味はなかった。
敷いて言えば暇潰し。
室内にいる気分でもないなら、外に散歩に出た方がマシだ。
けれど普段なら心地好いはずの静寂も、今は苛立ちを煽るだけに終わる。
無性に腹が立って仕方がなかった。
懐から藍色の布製の小袋を取り出す。
手の平の上で逆さにすれば、コロンと申し訳なさげに何かが落ちてきた。
その重みを感じるように握り締める。
冷たい金属性の質感が、死を握っている錯覚を起こさせる。
必ず帰りますから、と彼が残していったモノ。
彼の属性を司る、霧の指輪(リング)。
いつか帰る日まで預かっていてほしいと、そう残して彼は――六道骸は、僕の目の前から姿を消した。
何処に行ったのかも、何の為に消えたのかも、わからない。
僕は引き留めもせず、無言で彼を送り出した。
そもそも何の関係もない仲だ。
彼が何故僕に指輪を残したのかすら不明だった。
残すならば託すならば、霧の、あの子にでも渡せばいい。
それなのに彼は僕に渡した。
何故か、なんて僕が聞きたい。
受け取った僕も僕だ。
いつにない真摯な色を帯びた眼差しに、呑み込まれてしまうなんて。
「愚かなものだ」
つい自嘲が零れる。
――消えてから三年、まだ彼は姿を見せていない。
何か知ってそうな男に問い質したこともあるが、オレも連絡がつかなくて困ってるんです、とだけ返された。
嘘ではないだろう。
メリットがないし、何よりアレは成長しても嘘が吐けない。
否、仕事絡みでは見事にポーカーフェイスを繕うが、その他のことには弱かった。
もしかしたら彼の失踪は仕事絡みで、アレは何も知らないフリをしているのかもしれない。
だが、それが何だというのか。
結局答えを得られないなら考えるだけ無駄だ。
時間の思考の浪費だ。
だいたい僕はどうして彼の帰りに拘っているのか。
預かった指輪だって、別にあの子に押しつければいいだけだ。
きょとんとしながらも受け取るだろう。
彼女は彼の忠実な下僕なのだから。
主人の大切なモノを受け取らないわけがない。
そうだ、何も自分が持ってる必要はないじゃないか。
心中で言い聞かせてみても、実際に手放そうとすれば躊躇われた。
手の平の中から重みが消えてしまうのが、ひどく不快だった。
「わけがわからないよ、こんなの」
歩きながら小言を言うなんてどうかしている。
せっかくの静けさを自ら壊すなんて馬鹿げた話だ。
けれど長いこと内に留めておけるほど、些細なものではなかった。
どこから来るのかわからない衝動。
最初は気に掛けることもなかったソレは、彼の不在が続く中で募る一方で。
遣る瀬ない想いに駆られながら歩いていれば、肩に違和感を感じた。
神経を研ぎ澄ませていなければわからないぐらい、些細な。
「……?」
肩に触れたモノを、指先でそっと掴む。
けれど、摘んだ指の間で崩れた。
まるで砂のような感触だった。
鼻腔を擽る香は、何かを燃やした時に漂うものによく似ている。
――灰、か。
舞い落ちてきたのは。
五感を更に研ぎ澄ませたが、原因らしいものはこの周囲には見当たらない。
違うのか。
己の判断ミスか。
ただの砂が風に巻き上げられて、その欠片が落ちただけなのか。
いや……どうでも、いいか。
気づけば、彼の帰還に結びつけてしまっている自分がいて、苦笑した。
これではまるで恋煩いだ。
全く以て馬鹿げている。
特に音もなく舞うモノに対しては、愚かに過剰な程に敏感だ。
薄紅の花へと連想され、過日を呼び覚まさせる。
そうすれば必然的に、彼を意識せざるを得ないわけで。
「……君がさっさと帰ってくればいいだけなのに」
咄嗟に吐き捨てた言葉は震えていた。
唇を噛み締め、何も考えたくなくて激しく頭を振る。
思い出したくない、思い出したくない。
思い出すほどに、思い出となる。
『……恭弥、僕は必ず君の元に帰ります』
『来なくていいよ。そういうことは君の仲間とやらに言えば? だいたい何で僕に言うの?』
『その理由は君が一番知っていると思ったんですがね』
『僕が?』
『ええ。ですが、わからないのであれば帰ってから伝えますよ』
――だから、それまでこの指輪を持っていてください。
残された、交わした、初めての口づけだった。
僕がソレを頭で理解したのは、彼が目の前で霧に包まれて消えた後。
唇に刻まれた温もりが、今も未だ残留している。
何のつもりだとか、ふざけるなとか、いくらでも叫べたはずなのに――僕は、しなかった。
「むく、ろ……」
瞼を閉じれば、押し出された滴が零れて頬を伝う。
――愕然と、した。
「は……なに、これ」
指先で頬に触れ、滴を掬う。
濡れた感触に、何が起きたのか把握できなかった。
別に流したことが初めてというわけじゃない。
赤ん坊の頃には誰だって流すものだし、僕だけが例外と思っているわけでもない。
……問題は、何故、今なのか、だ。
どう考えてもおかしすぎる。
僕の中で色々と何かが壊れているんじゃないだろうか。
そうでなければ説明がつかない。
ただ、一瞬だけの、あの優しい熱を、堪らなく欲した。
「まるで、これじゃあ……ッ」
指先に僅かに残った灰を潰せば、質感は別のモノへと変化した。
花弁、暗闇でも仄かに光る、薄紅の花。
……どうして、この瞳は容易く幻を捉えてしまう?
「骸ッ!!」
衝動的に声を荒げれば、胸元に入れていた携帯が着信を唄った。
母校の校歌を遮るように、取り出したソレを開ける。
液晶画面に表示された着信元を見て……嫌な予感しか、しなかった。
「何か、用?」
問えば、ひどく沈んだ声が返ってくる。
途切れ途切れに、苦しそうに辛そうに、時折泣きじゃくりながら。
どうして、どうして、と繰り返す声は、耳障りでしかなかった。
苛々する。
腸が煮え繰り返る。
いや、これは……かな、しい?
「用件はそれだけ?」
「っ……あなたはっ、あなたは何とも思わないんですか!?」
「僕に関係ないしね」
「嘘ですっ! だってあなたは――」
抉じ開けられた、真実。
「……はっ。わらえ、ない」
言葉を搾り出すのもやっとという形で、電話を強制終了させた。
まだ何か言いかけていたことを思い出し、携帯を地面に勢い良く投げ捨てる。
静寂を突き破る激しい音と共に割れ、細かな部品が散らばった。
ぜいぜいと荒くなっていく呼吸が煩わしい。
「……必ず、必ず帰るって言ったくせにッ!!」
喉が潰れてしまいそうなほどに。
暗闇に融け入ることすら許さないかのように。
高く高く、怨み言を張り上げる。
知らず焦がれていた者の、永遠の喪失を知らされ、僕はその場に膝をついて崩れ落ちた。
【灰桜――焦がれし、先へ】
(焼き尽くされた身が遺した、約束。戻ると言わなかった君は、確かに還ってきた)
fin
- 12 -