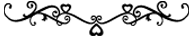風紀財団の屋敷内で、厳粛な静寂を纏う中庭。
喧騒とは無縁の、一種の聖地。
小石で縁取られた少し歪んだ丸い池には、赤白の鯉が優雅に泳いでいる。
されど水音は立たない。
耳を澄ましても、鳥の泣き声一つ聞こえなかった。
「――」
桜がほぼ散った樹を見上げ、雲雀は小さく呟く。
言葉に意味はない。
あるとすれば、足元に散乱する花弁の成れの果て。
地に落ちた姿さえ美しく思う。
やはりあのことがあっても、この花は自分が好きなものなのだろう。
そもそも和を好む自分が、芯からこの花を嫌悪できるわけがない。
……雲雀は些末な考えを追い払うように、軽く頭を振った。
「……」
背後に突き刺す視線を感じて振り返る。
本当はもっと前から気づいていた。
自分以外の気配に、風紀財団の者ではない気配に。
この花を背景に会いたくない人間に。
「よかったですね」
「何か用?」
どこか嘲ってくる男に、雲雀は素っ気なく返す。
意は解していた。
けれどそのまま察してやるほど、彼はお人好しでもなければ従順でもない。
「君の“嫌いな花”が散って嬉しいでしょう?」
わざわざ強調する辺り、嫌がらせの何物でもない。
思い出すでしょう、と暗に示しているのだ。
この男に弱味を握られたのは、雲雀にとって不運でしかない。
尤も――例のことがなければ互いに、恐らく一生出会うことはなかった相手。
様々な偶然が絡み合ったという以外にない。
ある意味では運命的。
雲雀は不愉快だと眉間に皺を寄せ、殺意を孕んで睨みつけた。
一瞬とはいえ、空気さえ震わす。
しかし悲しいかな、目の前の男には何の意味も成していないのだが。
「……」
時間の無駄だと悟り、雲雀はまた樹に向き直る。
足音が近づいたが、聞こえぬフリをした。
まだ数枚の花弁を遺している樹は、それでも満開と比べたら寂しい。
……春の終わりを感じさせるには充分だった。
「っ!?」
――意識を取られていた、そう雲雀が察した時は既に遅く。
後ろから抱き締められた身体は強張り、伝わる温さに小さく震えた。
「何のつもり?」
「嫉妬、ですかね」
「馬鹿馬鹿しい」
振り返ることなく切り捨てれば、男は目で柔らかく微笑む。
雲雀には見えていないが、それでも相手の表情が容易く想像できた。
恐らくソレが本音を隠すための嘘であろう、ということも。
「こっち向いてくれませんか?」
「……っ」
耳元で低く艶がかった声で囁かれ、雲雀は拳を握り締める。
脳髄に染み込むような、抗いがたい低音。
故に、絶対に聞いてやるものか、と力の入り方は語っていた。
仕方のない人……と男は苦笑し、さらに強く抱き締める。
僅かに骨が軋むほど、痛みは増し。
けれど雲雀は抵抗を止めない。
頑なな態度は、例え骨が折れたって……といったところか。
矜恃の高さは人一倍。
男もよく知る故に、恐らく要求は聞き届けられないだろう、と察せた。
だが相手のそんな面を気に入っていることも、また事実。
どうしようもない、と男は内心笑った。
「その花は忌まわしいですね。咲いても、散っても、君の心を捕え続ける」
「――ソレが、君絡みだとしても?」
おや、と男は目を細める。
また同じように一蹴されるかと思いきや、返されたのは予想外。
少しは関心を引けたのか。
彼の笑みが、醜い愉悦に染まる。
「ええ、だってソレは僕ではありませんから。無関係でなく間接的要因とはいえ、君を捕えるのは僕だけであってほしいんですよ」
「……我儘な奴」
暫しの沈黙。
後に振り返った雲雀は、綺麗すぎる笑みを浮かべていた。
呆れた意を孕みながらも、その様は今まで相手に向けた中で一番綺麗だったかもしれない。
「雲雀……」
意図を知らぬ儘、男は誘われるように口づける。
触れるだけの、されど次第に深くなっていく行為は、まるで互いの何かを満たすようだった。
【過日に舞う花になど、縛れるわけもない】
(もう僕はとっくに君に囚われているのに)
fin
- 13 -