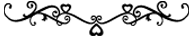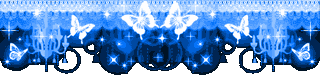

一部歌詞インスパイア→『ゆらめき』という曲です。アーティスト名は切なくなるので伏せます。
★★★★★★★★★★★
「――死になよ」
――応接室内、漆黒に染められたソファの上で重なる二つの影。
自分によく似た、銀髪の男の首に僕は手を掛ける。
彼は容易く囚われた。
力も経験も断然相手の方が上であるはずなのに。
彼は抵抗一つせず、静かに静かに笑った。
「殺しても構わないよ。できるものならね」
「みくびるな……ッ!!」
自分の手に指に力が込められているのがわかる。
怒りからか憎しみからか――それはわからない。
どれだけ力を入れても、彼は涼しげな表情を崩そうとはしなくて。
本当にこのまま絞め殺してやろうか――ああ、でも。
「……馬鹿馬鹿しい」
パッと手を放す。
あまりにも頭に血が上っていて忘れていた。
目の前の彼は、この憎たらしい男は――。
「既に、死んでるじゃないか……」
弱々しく呟く。
先程までの自分がひどく惨めで馬鹿みたいだ。
そう、ここにいるのは指輪に宿っていた思念が具現化しただけのもの。
つまり――本物の彼ではない。
ここにいる存在は魂ですらないのだ。
現実離れした話だが、あの草食動物と関わった時から常識など捨てている。
むしろそれを――自ら選んだのだから。
「ようやく思い出した?」
「目障りだ、消えろ」
「ああ、これからX世と会うんだっけ……」
すっかり忘れてたよ、とほざく彼を本気で咬み殺したいと思う。
今彼を殺そうとした原因が何かと問われれば、あの草食動物絡みだったというのに。
しかし時折枷が外れたように牙を剥き出しにする相手は――全く掴み所がなくて。
「君に護られるほど価値はなさそうだけどね」
「煩い。僕のやることに口を出すな」
「まあ――大空は化けるからちょうどいいのか」
「まだ戯言をッ!」
僕は彼に向けてトンファーを振り上げた。
忌々しい、忌々しい。
当たらないだろうと知っていても、殺したくて仕方がない。
息の根を止めるだけじゃ足りない。
四肢を八つ裂きにするぐらい惨く……。
「――X世の雲よ、その辺りでやめてもらえないか」
「「!?」」
僕も彼も驚いて窓の方を振り返った。
視界に入るのは、滑らかな金髪に、額にはあの草食動物に似た炎が灯る様。
僕は銀髪の上から退き、ゆっくりと立ち上がる。
銀髪もまた起き上がると、忌々しいとでもいうように金髪を睨みつけた。
「――ジョット」
「アラウディ、これ以上雲を苛めるな。オレたちは「死人、だろ。わかってるよ。この世には存在しないものだ」
――指輪が与えた気紛れ、本来ならば成し得ない出会い――それを奇跡などで括れはしない、のか。
「ねえ、さっきの「X世の雲よ、オレとX世は異なる存在だ。アレが同じ道を辿ることはないだろう」
金髪は優しく諭すように告げた。
彼の面影がある――けれど全くの別人。
威厳がある様は、自分が知る彼にはない。
「……あなたは誰なの?」
「継承の儀で……いや、お前に名乗ったところでどうせまた忘れるだろう。アラウディ、戻るぞ」
「――そうだね。偽善者の面を見てると殴りたくなってくるし」
「それはオレのことか?」
「どうかな。結局は化けた大空に変わりはない」
銀髪が再び言葉を繰り返せば、金髪はやれやれと溜息を吐いた。
困ったような、それでもいとおしんでいるような……けれど儚げで。
そう考えて、僕は一つの結論に辿り着く。
「……あなたたちは、恋人同士――だったの?」
僕の問いに、二人は弾かれたように顔を見合わせた。
恋人同士か……そう含み笑いを洩らしたのは銀髪の方で。
逆に金髪はひどく傷ついた表情をしていた。
今にも泣きそうな、それでも必死に堪えているような。
――地雷だったのだろうか。それを僕が知る術は当然なくて。
「……鋭いね。僕達は確かに恋人だったよ」
「……ッ」
銀髪の冷たい声色に、金髪は僅かに唇を噛み締める。
歪んだ顔は、明らかに続きを聞くことを拒んでいた。
崩れ落ちてしまいそうなほど痛々しい様――それはまるで、彼の表情にも似ていて。
だから、これ以上見ていたくなかったのかもしれない。
「――もういいよ。これ以上聞く気はない」
「優しいね。そんなに彼が――X世が傷つく顔は見たくない?」
「別にそういうわけじゃないよ。ただ――ムカつくだけ」
僕が吐き捨てれば、素直だねと銀髪は小馬鹿にしたように笑った。
苛立ちを覚えてトンファーを構えれば、それを遮るように金髪が前に出る。
「やめてくれ雲ッ!」
「邪魔するならあなたも咬み殺すよ。だいたい「君が僕を庇うなんてね、ジョット。これは免罪符――償いのつもり?」
向ける殺気は憎しみだけに留まらず、溢れんばかりのいとおしささえ孕んで。
愛故に――憎悪。
彼らの関係を言葉にするなら、それが妥当かもしれない。
けれど一つだけ確かなのは……。
「……あなたたちは、まだ――」
僕の言葉はそこで途切れた。
というより、声を発することができなかった。
どんなに口を動かしても、何一つ音にすることはできない。
まるで直に声帯を締めつけられた圧迫感。
異常に気づいて彼らを見据えれば、金髪がすまなそうに目を細めていた。
彼はそのまま僕の耳元に口を宛て、小さく囁く。
「オレはまだあいつを愛しているよ。だけど――もう無理なんだ。永遠に、この愛は戻らない……」
(――っ!?)
――愛より遥かに重い。
――裏切りの中で君は。
「だから、お前達は幸せになってくれ……」
金髪が僕から離れると、ようやく圧迫感から解放された気がした。
そのまま背を向けた彼に口を開こうとしたところで、銀髪は最大の憎しみを込めて吐き捨てる。
「君もどうせ同じ道を辿るに決まってる。その顔が、彼の顔が――この世で一番憎いと思うようになるんだよ」
――殺したいほどに、ね。
身体が引き裂かれそうなほどの劣情。
心が切り裂かれるほどの痛み。
それらを残して、彼らは消え去った。
二人がそれぞれ告げた言葉が、ぐるぐると頭の中を回り続ける。
あれがまだ自分達に似た存在ではなかったら救われただろうか。
他人事と受け止められただろうか。
彼らが未来の自分達に見えてしまうなんて――ああなんて感傷的。
「……それでも、僕には彼しかいないんだ」
孤高であったはずの自分がこんなにも執着する。
それはきっと愚かだ。
悲劇のフラグを自ら立てるようなものだ。
けれど手放せない、少なくとも自分からは。
否、もしかしたら殺してしまうかもしれない。
自分から彼が離れようとしたら――その時、銀髪が言っていたことが少しはわかるのだろうか。
そして彼に、あの子によく似た……。
「遅くなってすみませんヒバリさんっ!!」
ドアがバンッと勢い良く開け放たれ、三十分以上も遅刻してきた待ち人が現われる。
まったく、なんで今日に限ってこんなに遅いのか。
おかげで余計な疲れが溜まったじゃないか。
「君、遅いよ」
「すみません、補習が中々終わらなくて」
申し訳なさそうに謝る彼。
――これが化ける?
ますます信じられない。
虫も殺せないような……ああ、でもそんな彼に僕は魅かれたのか。
ならば牙を、まだ研いでいない牙を持っていてもおかしくはない。
草食動物でありながら肉食動物の素質を持つ、なんてアンバランスなのか。
「一日の半分以上は君のせいで疲れたよ」
「え? オレ、遅刻以外に何かしたんですか!?」
「……色々、ね」
含み笑いで返してやる。
正直、未来や先のことなど全く興味はない。
今があればいい、それを人は楽観的思考――或いは刹那主義と呼ぶのかもしれないけれど。
――それでも、今はどうかこのままで。
fin
- 3 -