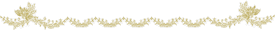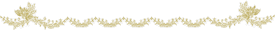
輝くネオンに煌めくグラス。
眠らない街とはよく言ったものだが、俺はもう眠りたい…。ああ、布団が恋しい。
連日残業続きの金曜日。今日こそは早めに帰ろうとしたのに、気がついたら上司の接待に付き合わされることになった。
お得意先に酌をすること2時間…散々「君は暗いなぁ!若いんだからもっと覇気を出さないと!」「そんなんじゃモテないぞ〜!それとも君、童貞かい?ガッハッハッ!」「何〜?おっぱいに興味ないの?ボカァまだ興味あるけどなぁ…ハッハッハッ」などとセクハラ混じりに揶揄されても尚、愛想笑いをしてきたのだがもう限界だ…。
死んだような目は生まれつきである。
だが、今日はもっとやばい目をしている自信がある。
ようやくお開きになろうとした時、得意先のクソセクハラ親父が言ったのだ。
「せっかくだから夜遊びというものを教えてあげよう!いいお店を知っているんだ」
おっぱいもお尻もいりません。
キャバなんてコミュ障の俺にとっては拷問だ…。なんでこの年代の親父はそういうのが好きなんだ…。
ドギツイ紫の壁に真っ赤な店名『Rosaria of a secret』かなり裏手の方に来たのでひょっとしたらただのキャバじゃなくて、おさわり系の店かもしれない…ああ、このセクハラ親父ならありそう…人前で赤の他人とイチャつくなんて…ああ、鬱だ。上司にネタにされるだけだ…。
「「いらっしゃいませ〜〜」」
重たい扉を開けると、キラキラギラギラ?したカラフルなイケメン達が並んでいた。
ひっ…
「ハッハッハッ驚いたかい?ここは男性の為のホストクラブさ。女の子じゃなくて悪かったね」
得意先のおっさんは、慣れたように1人のホストと話すと席へ案内された。
「まぁ、たまには君も誰かに話を聞いてもらいなさい。我々はBIP席で飲んでるから…」
そう言って2人は奥の方の席へ行ってしまった。金髪のホストと俺を残して。
え、ええー!?
「どうもーお兄さんコンニチハー!」
あー、たしかにホストって人の話聞いて、めちゃくちゃ褒めてくれるからそれが気持ちいいって聞いたことあるなー。
って、でもそれってこっちにもある程度コミュ力必要じゃん!?結局キャバと一緒だよ!!余計気まずいわ!!
仕方なくうっすい水割りをチビチビと飲む。
はぁ…それにしてもイケメンだ。
金髪も黄緑のメッシュも、コバルトブルーのスーツも常人じゃ似合わないよな。
俺もこんなイケメンだったらこんな根暗な性格じゃなかったのかもしれない。
などと、ぼんやり思っていたところだった。
「ねぇ、ひょっとして溜まってる…?」
男臭く目線を寄越すイケメンに、不思議に思いながらその先を辿るとなんと元気になっている息子がいるではないか…!
は、恥ずかしい…!!
「つつつ…疲れマラってやつ…?かな…すみません…その、このところ忙しくて…」
恥ずかしい…こんなイケメンの前で勃起するなんて…
ああああ、神さま…こんな俺から睡眠時間だけじゃなく男としての尊厳まで奪うなんて…あまりにも残酷な…。
恥ずかしいやらなんやらで、放心状態の俺を横に、何やらイケメンホストは目を輝かせている。
「ねぇ、嫌じゃなかったらしゃぶってあげようか?結構上手いよ、俺」
そう言いつつ、椅子から降りて俺の太ももに手を置いてきた。
な、な、な、な!?
「ちょ、ちょっと…!こ、こんな…お店で…!?」
焦りながら金髪頭を抑える。
整髪剤なのか香水なのかわからないが、男の匂いがふわりと香る。
同じ男なのにいい匂いがするな、とクラクラしながら思った。
「ん、だって『男の為の』ホストクラブなんだから…楽しんでもらわないと…っ!」
『男の為の』ってそういう意味!?
あ、あのセクハラ親父ぃ…!!!
じゃあ今頃彼らもさっきのホスト達とこんなことしてるってこと!?
パニックになって、目を白黒させながらわたわたしているうちにズボンのジッパーが下がる。
「あっ…」
パンツの上から口に咥えると、そのまま口を使ってパンツをズラす。
その仕草だけでもうこっちは目の毒だ。
女性にさえやってもらったことのないエロい行為だ…。
最初はチロチロと舐めるように、次第に舌を絡ませながら喉の奥へと誘っていく。
「んっ…ふ…」
気持ちよすぎて声が出そうだ…
力んだせいで、ふいに足先が彼の股に当たってしまった。
「「あっ…」」
声を出したのは俺だけじゃなかった。
金髪は、俺のをしゃぶりながら自身の下半身を熱くしていたのだ。
「はっあ…!ねぇもっと踏んでよ…」
「は、は!?え?よ、よ、汚れるよ?」
無論そんなことどうでもいいんだろうけど、俺が嫌だ。そんなSMみたいなこと…。
「…はぁっ、ねぇ、そのくたびれた靴で俺のここ踏んで…?俺の高いスーツ、君ので汚して…?」
上目遣いで煽るイケメン。
てか…
「…くたびれたって…客に対して失礼じゃないの…?」
「んああ…!」
少し強めに股間を踏んでやる。
コバルトブルーのスーツが汚れようが構うものか。
コイツの言うことにノッてしまうのは、些か腹が立つが、踏めば踏むほど、しゃぶり方が激しくなってくる。
「…ん!」
俺はもう何も考えられず、頭を鷲掴みにし、まるでオナホを使うかのようにガンガンと動かした。
それなのに、気持ち良さそうにこちらを見上げてくるその瞳に…キた。
「……っ!」
俺が頭を抑える直前に、金髪が自ら全て頬張った。その瞬間そいつの喉奥で果ててしまった。
全て出し切ると、ゆっくり口をすぼめながら口から離した。
「ん…いっぱいでた…ぁ…」
それは口の中のことなのか、はたまたそのスーツの中のことなのか。
まるで夢の中の出来事のようで、何も考えられなかった。
しばらく放心していると、遠くから上司たちが向かってくるのが見えた。
「ハッハッハッ…なるほど、助かったよ。今度取引する相手がワイン通でね…店選びに苦労してたんだ。流石カナト君は色んな店に精通してるなぁ…おや」
いつの間にか俺の身支度まで、整えた金髪はしれっと見送りの準備をしていた。
「君も会話を楽しんだようだね。顔がさっきより明るくなってる…」
「いやぁ、中々良いものですねぇ。久しぶりに『すごいですね』って言われましたよ」
「そんなそんな、君は女の子にもいっぱい言われてるだろ?」
「君もこれで少しは社交が身についたかなぁ?」
上司たちの会話が遠く聞こえる。
「ありがとうございましたー」と挨拶するホストたちの声も、扉が開く音も。
どれも現実離れしている。
ふらふらとなりながら、上司の後に続く。
その瞬間ー。
「また来てね」
突然肩を寄せて囁いたその声が、胸ポケットに忍ばせた彼の名刺が、これは現実なんだと叫んでいた。
眠らない街を歩きながら、ああ、早く布団に入って眠りたいと思った。
眠って起きて、早く悪夢から目を覚ましたかった。
- 16 -