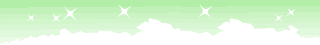
「不味いな」
オレはフォークを置いた。
リゼルグが信じられないと言う目でオレを見た。
「ホロホロくん…?」
彼の大きな目が更に大きく見開かれて、それはオレを捉えていた。
出されたのは数々のイギリス料理。
作ったのは他でもない リゼルグだ。
寝坊したオレに一生懸命作ってくれたんだろうけど、二口 口に運んだあと、オレはフォークをテーブルに置いた。
「ひどい…せっかく作ったのに…」
不機嫌そうに眉を潜ませ、目を細めた。
小さく謝って、味がしないと訴えたら
「そんなに嫌なら自分で味付けすれば」
とコショウと塩を差し出され、なんとも無愛想に言われた。
オレは黙ってスコーンに手を伸ばし、味付けを変えずに出されていたブルーベリージャムを付けて口へと運んだ。
「……」
完全に怒りモードの奴は、オレがそれを食べているのに目もくれない。
「悪かったって…。」
「別に…」
「…だから、お前の料理が下手だとか言いたいわけじゃなくて、イギリス料理自体あんまり美味くねぇんだって…。」
「………。」
いつまでも黙り込む奴がじれったくて、思わずキスをしてしまった。
唇と唇が触れるだけの柔らかいキスからだんだん激しくなった。
ろくにキスなんかしたことないのに、その場のノリだけでキスを終えて 離した頃にはもう
リゼルグは怒ってなかった。
「…っホロホロくん」
恥ずかしそうに赤くなった頬が愛しかった。
不覚にも、自分だけのモノにしたい なんて
そんな事を思ってしまうんだ…。
恋人でもなくて、決して二人 好意を示してる訳でもないのに
何故だか、欲しかった。
これから出掛けないといけないのに理性は言うことを聞かなくなってた。
そんな言い訳を考えて、気がついたらオレはリゼルグを壁に押し付けて 身動きを取らせないようにしていた。
「……っ」
今更我に帰ったって退きようがない。
後には退けない…
オレはもう一度だけ、リゼルグにキスした。
小さいくもった声が耳に入ると不安が途切れた。やるなら今しかない。
ご丁寧にリゼルグの服を剥いでズボンを下ろした。
彼の乳首はもう固くなってて、凄まじいほどの興奮がオレを襲った。
唇でくわえて小さい粒を舌で転がすと、彼の口から甘い声が小さく漏れた。
欲しい
早くコイツが欲しい。
今、何よりもそう強く願った。
口から漏れる甘い声を隠す為 と口実に指を口に押し込んで舐めさせた。
「ふ、ぁ…んん…っ」
オレの人差し指と薬指が唾液で濡れる。
その指を自分の自身に持っていって自ら濡らした。
「リゼルグ…後ろ向いてケツこっちに突き出せ…。」
興奮を抑えながら、わざとクールに言ってみた。
リゼルグは小さく頷き、言われた通り 実行した。
「…ホロホロくん、」
不安げにオレを見る緑色の瞳。
構わすに自身を蕾にあてがった。
何かを言おうとしていた彼の言葉に耳を傾けず、少しずつ中へ入って行く
―――ズブ、ズズズ…
「んぁあ…あ、ひ…っ」
苦しそうに顔を歪めるリゼルグ。
そんな顔を見て、ますます興奮するオレはなんだか恥ずかしがった。
ズブズブと真ん中あたりまで一気に入れて、少し休んだ
リゼルグの顔に目を向ければ彼の目に涙が沢山溜まっていた。
「あ…ん…ホロホロ、くん…っ」
ギチギチと肉と肉が擦れる音が生々しい。
「力入れるな…っキツい…ハァハァ」
「ぅああ…だ、だって…ぁ、ひぃ…っ」
オレが動く度に苦しい声が聞こえた。
「は、初めてだから、もっと優しく…して…っ」
リゼルグの言葉に耳を疑った。
初、めて…?
だからあんなに痛がってたのか なんて、今更だけど考えて 反省した。
耳元で呟くようにして謝って、今度はゆっくり丁寧に挿入を続けた。
すると、リゼルグの喘ぎは前とは違ってただただ甘い、ハチミツみたいな声になった。
それから、オレの自身が全部中へ入ったのは10分も後のこと。
初めてを奪ってしまったのと、リゼルグの頬が紅く染まっていたせいで
もう離したくない
と 錯覚をしてしまった。
―――翌日
「やべえ、遅刻するっ!!」
「おはようホロホロくん」
挨拶もそこそこにオレは玄関へ向かい靴を履いた。
「…行ってくるぞ、リゼルグ」
ボソッと言った。
名前を呼ぶのが少しだけ 照れくさかったからだ。
「うん。気をつけてね!」
目を閉じて笑った顔が可愛かった。
「いってらっしゃい」
そう言ってオレの唇にキスをくれた。
恋人のお見送りのキスは何よりも有り難いオレの糧
「いってきます」
出てったドアがバタンと音を立てて閉まった。
- 4 -
戻る
