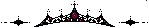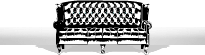それはまるで雪の様で
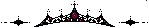
─迎えに来たよ─
 それはまるで雪の様で
それはまるで雪の様で
夢を見た。
幼い頃、何度も何度も見た夢。
「誰?」
声のする方を向いても誰も居ない。
誰も。
『雪ちゃん』
「誰?」
ぐるぐると辺りを見渡すが、やはり誰一人としてこの空間に居ない。
「誰なの?ねぇ!」
今、居るこの空間は真っ白く何処までも広い。
何処までも。
その言葉への返答はなかった。
「見えないの?僕が」
「え?」
先程よりも近くに聞こえる。
「此処に居るじゃない」
「!!?ひっ」
身体に冷たい感触。
抱き締められていると思うには少し時が掛かった。
「なな何?」
「何って抱き締めてあげてるんじゃないか。君は孤独なんだろ?」
孤独。
違うと云えば嘘になるが、実際、その通りでもある。
養父や修道院の者達と共に生活をし、家族と断言しても正しい筈が、何処かでソレを否定している自分が居るのも事実。
自分には何の取り得もない。
双子の兄は逆に力があり過ぎてしまう。
"兄の様に力があれば"と何度思った事か。
そう思った夜に必ずこの夢を見るのだ。
『何?じゃなくて、本当は雪ちゃんだって分かってる癖に。知らないフリをするなんて』
しかし、夢は温度や五感に関するモノはあまり体感しないと聞いたが、どうなのだろうか。こうして、自分に触れているモノは雪の様に冷たい。
首にツゥっと舐められる。
「冷たっ。雪みたい」
『やっぱり今はまだ早いかな。だけど、覚えといて?大きくなったらまた会いに来るから』
冷たさに目を閉じ、再び目を開けると、夢の中の人物はソレを云い残し消えていった。
「え?」
上手く聞き取れなかった雪男は首筋に残っている冷たい感触に手を添えた。
「…冷たい…」
それはまるで雪の様に冷たかった。
やがて、十五歳となった彼がまたあの人物と会うのは数年後の話。
終。
2011*08*29
-umi-
幼少雪男君と悪魔の力が未覚醒の雪男君の話。
本人は誰と会い、会話をしたのか成長するにつれ忘れてしまいます。
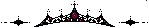 戻る
戻る
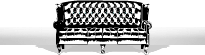
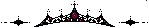
─迎えに来たよ─
 それはまるで雪の様で
それはまるで雪の様で
夢を見た。
幼い頃、何度も何度も見た夢。
「誰?」
声のする方を向いても誰も居ない。
誰も。
『雪ちゃん』
「誰?」
ぐるぐると辺りを見渡すが、やはり誰一人としてこの空間に居ない。
「誰なの?ねぇ!」
今、居るこの空間は真っ白く何処までも広い。
何処までも。
その言葉への返答はなかった。
「見えないの?僕が」
「え?」
先程よりも近くに聞こえる。
「此処に居るじゃない」
「!!?ひっ」
身体に冷たい感触。
抱き締められていると思うには少し時が掛かった。
「なな何?」
「何って抱き締めてあげてるんじゃないか。君は孤独なんだろ?」
孤独。
違うと云えば嘘になるが、実際、その通りでもある。
養父や修道院の者達と共に生活をし、家族と断言しても正しい筈が、何処かでソレを否定している自分が居るのも事実。
自分には何の取り得もない。
双子の兄は逆に力があり過ぎてしまう。
"兄の様に力があれば"と何度思った事か。
そう思った夜に必ずこの夢を見るのだ。
『何?じゃなくて、本当は雪ちゃんだって分かってる癖に。知らないフリをするなんて』
しかし、夢は温度や五感に関するモノはあまり体感しないと聞いたが、どうなのだろうか。こうして、自分に触れているモノは雪の様に冷たい。
首にツゥっと舐められる。
「冷たっ。雪みたい」
『やっぱり今はまだ早いかな。だけど、覚えといて?大きくなったらまた会いに来るから』
冷たさに目を閉じ、再び目を開けると、夢の中の人物はソレを云い残し消えていった。
「え?」
上手く聞き取れなかった雪男は首筋に残っている冷たい感触に手を添えた。
「…冷たい…」
それはまるで雪の様に冷たかった。
やがて、十五歳となった彼がまたあの人物と会うのは数年後の話。
終。
2011*08*29
-umi-
幼少雪男君と悪魔の力が未覚醒の雪男君の話。
本人は誰と会い、会話をしたのか成長するにつれ忘れてしまいます。
- 17 -