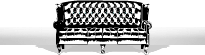ポインセチアとあんよが出来ない仔ヤギ
 可哀相に。あんよが出来ないでいる仔ヤギが鳴いている。メェメェと。本当は、あんよが出来る筈なのに主がそれを出来なくさせている。嗚呼、何と嘆かわしや。
可哀相に。あんよが出来ないでいる仔ヤギが鳴いている。メェメェと。本当は、あんよが出来る筈なのに主がそれを出来なくさせている。嗚呼、何と嘆かわしや。
 ポインセチアとあんよが出来ない仔ヤギ
ポインセチアとあんよが出来ない仔ヤギ
「本当にお前が、あの"ガンダム"に乗っているなんて信じられないよな」
「俺だって信じられません。まだ実感が無くて」
地球にあるリディの実家。本来なら彼が嫌いな父親もこの家に居るが、仕事で長期世界各地へ出張に赴いている。なので実質、マーセナス家に今、居るのは彼と居候としてマーセナス家にやって来た少年の二人のみになる。入隊してから、この家には何年も帰ってきていない。宇宙艦やロンドベルの寮が全体を占める。そんな父親嫌いな彼が何故、帰ってきたかと云うと、父親が長期不在の一報を聞きつけたからだ。関節的ではなく、直接電子メールが送られてきた。送り主の文字を目にした瞬間、粟肌が立った記憶は数日経過した今でも鮮明に覚えている。読まずに削除しようとさえ思ったが、目を通すだけしてみた。すると、─長期不在─の用件が書かれた文面の変哲の無いメールであった。わざわざこんな事で見たくもない男の名前を見てしまった。遠回しに、─父親の私が居ない間位は家に帰ってこい─と云う地上に居る息子への想いやりが隠れていた事は、彼には一滴の雫ほどにも思わなかった。そんな文面にしようなどと、父親もしていなかった為、親子の距離が縮まる事は無かった。
帰る家を持たない少年は彼の家に父親が不在の間だけ居候させてもらう事になった。ただの友達の家に住まわせてもらう、それが少年の心にあった気持ちだった。彼には少年ちは違う気持ちで家に居候させたとは、少年にはまだ気付かれてはいなかった。
「そんな事より、紅茶飲むか?」
「はい」
「えーと、紅茶の葉っぱとカップはどこだったか…」
フル・フロンタルと面会した際のフワフワなソファの感触が此処でも感じられた。高級な革張りのカボチャ色。ソファの感触に感動していた少年は、彼が何やらゴソゴソと探し物をしている事に気が付いた。
「見つからないんですか?」
「ああ。この間まではこのあたりにあった筈なんだが」
「それっていつの頃ですか」
"この間"と云っても、もう何年も前になる。少年に云われて「だいぶ前だな」と頷いている。そんな彼に呆れた様に溜息を吐いて一緒に探し始めた。
「あまり人の家の物を物色するのは気が引けます」
「なら俺が探すから、お前は休んでろよ。疲れてるんだろ?」
隣の棚、その隣の棚へと扉を開けるがそれらしき物は見つからない。
「リディ少尉だって疲れているでしょ?俺よりも」
「これでもパイロットで軍人だ。多少の疲れなんて気にしていられない」
「…なら、俺はお言葉に甘えて休ませてもらいます」
切りの良い所で少年は引き上げとうとしたら、制止の声が鼓膜を突いた。
「最後まで付き合ってくれないのか?」
眉間に皺を寄せながら振り向いた少年。彼は悪気無しといった顔でヘラヘラしている。優しい少年なのを知っている彼は踵を返してくれる確信があった。
「やっぱり、お前は優しいなぁ」
「リディ少尉が探していたら日が暮れそうな気がしたので」
「日が暮れるってまだ三時間くらいあるぜ?」
「もうほぼ全部キッチンを探しましたよ?」
「答えになってない」
「そうですか?」
三十分以上探したが、紅茶関係の代物は見つからなかった。
「ここまで探して見つからないのも、この家が広いからですかね。それか品切れなのか」
「嫌味か?」
「いえ」
「執事でも居れば良いんだけど。仕方無い、これから買い物に行くか」
「え?」
「折角だから、バナージのカップや皿なども買い揃えといた方が良いだろ?洋服も幾らエアー洗浄したからって云っても、それだけじゃ不衛生だし。好きな物買ってやるよ」
リディの提案に躊躇ったが、きっと一ヶ月程はこの家にお世話になると思うので買い物に付き合う事にした。
「本当に必要な物しか買いませんから」
「遠慮してるのか?」
「俺の手持ち、そんな無いから」
財布の中身を確認すると、やはりそこまでの大金は残っていなかった。
「お金の事は良い。全部俺が出す」
「え、でも、」
「子どもは大人に甘えて良いんだ。これは貸しでも何でも無い。気にするな」
「…はい」
彼は車の鍵と財布、携帯を持ち少年を外に連れ出した。車なら多少荷物が多くなったとしても大丈夫だ。
「有難うございます」
「礼は良い。行くぞ?」
「はい」
助手席に座った少年はシートベルトをキュッと握りしめた。
「どうした?」
「車に乗った事がほとんど無いので…」
「そうなのか。安心しろ。ガンダムに乗ってる時に比べれば何て事ないさ」
「はい」
彼は少年の気を少しでも紛らわそうと音楽を流そうと思い付く。
「何聴きたい?」
「何でも」
「何でもって…。じゃぁ、彼女に似たナツメ・スワンソンにするか?」
「なつめ?彼女?」
目を丸くする少年。
「そうだった。バナージは丁度その時、怪我してたんだったな」
ユニコーンから少年をハッチを開ける作業中にそんな会話をしていた。少年にはその会話の内容すら知らないので当然であった。
「オードリー、いや、ミネバがそのナツメ・スワンソンって云う女優に似ててさ。すっごい美人なんだ」
「そうなんですか」
「最近、歌手活動もし始めて」
綺麗なピアノの音色と共に澄んだ声が聴こえてきた。確かに、顔は見た事は無いが声は優しさと妖艶さを兼ね揃えていている。オードリーに似ているならきっと美人な女優なのだろうと少年は思う。
「クラシックですか?」
「ビンゴ。クラシックの曲で、彼女が作詞、作曲でアレンジされている」
「題名は分からないけど、聴いた事はあります」
「主に"恋"の曲が多い」
「恋…」
"恋"と云う単語に少年は胸の奥がざわめくのを感じた。
「な?良い曲だろ?」
「結ばれないんですね」
それがこの曲を聴いた率直な感想だった。内容は悲恋を歌ったもので、だが、暗さは感じられない。
「ああ。身分差で決して結ばれない。お互い愛し合っているのにな」
「よくある話ですよね」
いつの間にか手にしていたハロを撫でながらナツメ・ソワンソンのイメージを膨らませる。
「よくある話か…。ま、身分差は関係なくても、俺達も実らない"恋"をしたよな。ミネバに」
「そ、それはリディさんさんだけでしょ?」
「嘘吐くなよ。バナージだって惚れてたんじゃないのかよ」
赤信号で停止したリディは右手を伸ばし、ハロに手を添えているバナージの上に置く。
「お互い、惚れた女に弱いって事にしておくか。彼女の為に行動を起こしても、結局、自己満足でしかなかった」
「だから俺は別に…」
「認めないのか?好きだったって事を」
緑に変わり、車は発進する。リディはバナージの手をポンポンと叩き、手を離した。
「恋愛に関しては無頓着なのも良いが、もっと関心w持った方が良い。"恋"に溺れる位にな」
「…リディさんは、そう云うのになった事あるんですか?」
次のトラックになり、曲名が─溺れる"恋"に偽りは無し─と表示された。それを見たリディは画面を指差し、バナージは視線を向ける。
「この通りさ。一度溺れた"恋"をするとその気持ちに偽りなく相手を好きになる」
「そんなモノですか?」
「ああ。お前も溺れる様な"恋"をしたら分かる」
「…そうですね」
気付くとショッピングセンターに着いていた。耳に馴染んできていたナツメ・スワンソンの歌声を名残惜しむ様に二人は車を降りた。
─"恋"に目覚めない仔ヤギは"恋"と云うあんよがまだ出来ない─
終。
2011*12*09
-umi-
R-18の予定が健全になる不思議。 戻る
戻る
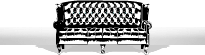

 ポインセチアとあんよが出来ない仔ヤギ
ポインセチアとあんよが出来ない仔ヤギ
「本当にお前が、あの"ガンダム"に乗っているなんて信じられないよな」
「俺だって信じられません。まだ実感が無くて」
地球にあるリディの実家。本来なら彼が嫌いな父親もこの家に居るが、仕事で長期世界各地へ出張に赴いている。なので実質、マーセナス家に今、居るのは彼と居候としてマーセナス家にやって来た少年の二人のみになる。入隊してから、この家には何年も帰ってきていない。宇宙艦やロンドベルの寮が全体を占める。そんな父親嫌いな彼が何故、帰ってきたかと云うと、父親が長期不在の一報を聞きつけたからだ。関節的ではなく、直接電子メールが送られてきた。送り主の文字を目にした瞬間、粟肌が立った記憶は数日経過した今でも鮮明に覚えている。読まずに削除しようとさえ思ったが、目を通すだけしてみた。すると、─長期不在─の用件が書かれた文面の変哲の無いメールであった。わざわざこんな事で見たくもない男の名前を見てしまった。遠回しに、─父親の私が居ない間位は家に帰ってこい─と云う地上に居る息子への想いやりが隠れていた事は、彼には一滴の雫ほどにも思わなかった。そんな文面にしようなどと、父親もしていなかった為、親子の距離が縮まる事は無かった。
帰る家を持たない少年は彼の家に父親が不在の間だけ居候させてもらう事になった。ただの友達の家に住まわせてもらう、それが少年の心にあった気持ちだった。彼には少年ちは違う気持ちで家に居候させたとは、少年にはまだ気付かれてはいなかった。
「そんな事より、紅茶飲むか?」
「はい」
「えーと、紅茶の葉っぱとカップはどこだったか…」
フル・フロンタルと面会した際のフワフワなソファの感触が此処でも感じられた。高級な革張りのカボチャ色。ソファの感触に感動していた少年は、彼が何やらゴソゴソと探し物をしている事に気が付いた。
「見つからないんですか?」
「ああ。この間まではこのあたりにあった筈なんだが」
「それっていつの頃ですか」
"この間"と云っても、もう何年も前になる。少年に云われて「だいぶ前だな」と頷いている。そんな彼に呆れた様に溜息を吐いて一緒に探し始めた。
「あまり人の家の物を物色するのは気が引けます」
「なら俺が探すから、お前は休んでろよ。疲れてるんだろ?」
隣の棚、その隣の棚へと扉を開けるがそれらしき物は見つからない。
「リディ少尉だって疲れているでしょ?俺よりも」
「これでもパイロットで軍人だ。多少の疲れなんて気にしていられない」
「…なら、俺はお言葉に甘えて休ませてもらいます」
切りの良い所で少年は引き上げとうとしたら、制止の声が鼓膜を突いた。
「最後まで付き合ってくれないのか?」
眉間に皺を寄せながら振り向いた少年。彼は悪気無しといった顔でヘラヘラしている。優しい少年なのを知っている彼は踵を返してくれる確信があった。
「やっぱり、お前は優しいなぁ」
「リディ少尉が探していたら日が暮れそうな気がしたので」
「日が暮れるってまだ三時間くらいあるぜ?」
「もうほぼ全部キッチンを探しましたよ?」
「答えになってない」
「そうですか?」
三十分以上探したが、紅茶関係の代物は見つからなかった。
「ここまで探して見つからないのも、この家が広いからですかね。それか品切れなのか」
「嫌味か?」
「いえ」
「執事でも居れば良いんだけど。仕方無い、これから買い物に行くか」
「え?」
「折角だから、バナージのカップや皿なども買い揃えといた方が良いだろ?洋服も幾らエアー洗浄したからって云っても、それだけじゃ不衛生だし。好きな物買ってやるよ」
リディの提案に躊躇ったが、きっと一ヶ月程はこの家にお世話になると思うので買い物に付き合う事にした。
「本当に必要な物しか買いませんから」
「遠慮してるのか?」
「俺の手持ち、そんな無いから」
財布の中身を確認すると、やはりそこまでの大金は残っていなかった。
「お金の事は良い。全部俺が出す」
「え、でも、」
「子どもは大人に甘えて良いんだ。これは貸しでも何でも無い。気にするな」
「…はい」
彼は車の鍵と財布、携帯を持ち少年を外に連れ出した。車なら多少荷物が多くなったとしても大丈夫だ。
「有難うございます」
「礼は良い。行くぞ?」
「はい」
助手席に座った少年はシートベルトをキュッと握りしめた。
「どうした?」
「車に乗った事がほとんど無いので…」
「そうなのか。安心しろ。ガンダムに乗ってる時に比べれば何て事ないさ」
「はい」
彼は少年の気を少しでも紛らわそうと音楽を流そうと思い付く。
「何聴きたい?」
「何でも」
「何でもって…。じゃぁ、彼女に似たナツメ・スワンソンにするか?」
「なつめ?彼女?」
目を丸くする少年。
「そうだった。バナージは丁度その時、怪我してたんだったな」
ユニコーンから少年をハッチを開ける作業中にそんな会話をしていた。少年にはその会話の内容すら知らないので当然であった。
「オードリー、いや、ミネバがそのナツメ・スワンソンって云う女優に似ててさ。すっごい美人なんだ」
「そうなんですか」
「最近、歌手活動もし始めて」
綺麗なピアノの音色と共に澄んだ声が聴こえてきた。確かに、顔は見た事は無いが声は優しさと妖艶さを兼ね揃えていている。オードリーに似ているならきっと美人な女優なのだろうと少年は思う。
「クラシックですか?」
「ビンゴ。クラシックの曲で、彼女が作詞、作曲でアレンジされている」
「題名は分からないけど、聴いた事はあります」
「主に"恋"の曲が多い」
「恋…」
"恋"と云う単語に少年は胸の奥がざわめくのを感じた。
「な?良い曲だろ?」
「結ばれないんですね」
それがこの曲を聴いた率直な感想だった。内容は悲恋を歌ったもので、だが、暗さは感じられない。
「ああ。身分差で決して結ばれない。お互い愛し合っているのにな」
「よくある話ですよね」
いつの間にか手にしていたハロを撫でながらナツメ・ソワンソンのイメージを膨らませる。
「よくある話か…。ま、身分差は関係なくても、俺達も実らない"恋"をしたよな。ミネバに」
「そ、それはリディさんさんだけでしょ?」
「嘘吐くなよ。バナージだって惚れてたんじゃないのかよ」
赤信号で停止したリディは右手を伸ばし、ハロに手を添えているバナージの上に置く。
「お互い、惚れた女に弱いって事にしておくか。彼女の為に行動を起こしても、結局、自己満足でしかなかった」
「だから俺は別に…」
「認めないのか?好きだったって事を」
緑に変わり、車は発進する。リディはバナージの手をポンポンと叩き、手を離した。
「恋愛に関しては無頓着なのも良いが、もっと関心w持った方が良い。"恋"に溺れる位にな」
「…リディさんは、そう云うのになった事あるんですか?」
次のトラックになり、曲名が─溺れる"恋"に偽りは無し─と表示された。それを見たリディは画面を指差し、バナージは視線を向ける。
「この通りさ。一度溺れた"恋"をするとその気持ちに偽りなく相手を好きになる」
「そんなモノですか?」
「ああ。お前も溺れる様な"恋"をしたら分かる」
「…そうですね」
気付くとショッピングセンターに着いていた。耳に馴染んできていたナツメ・スワンソンの歌声を名残惜しむ様に二人は車を降りた。
─"恋"に目覚めない仔ヤギは"恋"と云うあんよがまだ出来ない─
終。
2011*12*09
-umi-
R-18の予定が健全になる不思議。
- 3 -