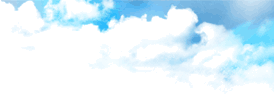
ご飯を食べて、お風呂に入って、部屋でゴロゴロして。そろそろ寝ようかと思ったところで、何故か急にアイスが食べたくなった。眠たくて体がぽかぽかしてるからかな、きっとそう。室内にある私専用の冷凍庫を開けるが、その中は空っぽだった。何か代わりになそうなものはと冷蔵庫を漁ってみるものの、出てきたのは魚肉ソーセージが一本だけ。どうやらアイスを食べるなら買いに行くしかないようだ。とはいえお風呂で全身綺麗にしたところなのだ、できることなら外には出たくない。だけど、口内はもうアイスを求めて寂しそうに乾いていた。このままベッドに入ってもアイス食べたさに眠れないに違いない。こういう時は実行するに限る。
「よし、アイス買いに行こう」
寝間着は黒いティーシャツにスウェットだから、上着を羽織ればちょっと外に行くくらいは問題ない。ハンガーにかかったお気に入りのパーカーを着て、スマホと小銭が入ったがま口をポケットに突っ込んで部屋を出た。
寮の玄関に備え付けられたセンサー式の電灯が私を照らす。それについ視線をやってしまって目の前がチカチカした。部屋の電気を消した中で見るスマホの画面とか、夜道に突然現れる街灯とか、そういった光に昔から弱いのだ。
目を眇めてなんとかやり過ごす。自分の体質はよく理解しているのにどうしてこう馬鹿の一つ覚えみたいに目線を向けてしまうのか。溜息をつきながら靴を取ろうとしてくつ下を履くのを忘れてきたことに気付いたから、スニーカーはやめてサンダルに足を入れる。ちゃんと履けたことを確認していざ外へ出ようと扉に手をかけた時、背後で何かが動く気配がした。
「あれ、名前さんじゃん。こんな時間にどうしたの?」
振り返るとラフな格好をした悠仁がいた。やぁ、と手を上げると悠仁も手を上げて返してくれる。
「アイス買いにコンビニへ。悠仁こそ、今から出掛けるの?」
「えっ、まぁちょっと……。てか名前さん、一人で行く気?こんな時間に?」
悠仁がつかつかと詰め寄ってくる。気圧されつつ、そのつもりだけどと返すと、彼ははぁ、と盛大な溜息を漏らした。
「それ、俺も行くよ。むしろ行かせて」
「う、うん……いいけど」
私の了承を得た悠仁は手早く靴を履き「行こ」と声を掛けてくる。頷いて歩き出すと、悠仁はあ、と吐息のような小さな声を落とした。パーカーのポケットに入っていた手を出してズボンでゴシゴシと拭いたかと思えば、その手を私に向けて差し出してくる。私は無言でその手を取った。きゅっと握りしめてどちらからともなく歩き始める。
多分手汗を拭ったのだろうけど、そんなもの私は気にしないのに。そういうところを気にする彼が可愛くてくすくす笑うと、悠仁は不思議そうにこちらを見てきた。
「なんか面白いことでもあった?」
「ううん、ふ、ふふっ」
「答えになってねぇし」
納得いってなさそうな悠仁の手を引いて「行こ!」と走り出せば、彼は仕方ないなぁという表情でついてきてくれた。
この道は街灯がないせいで暗く、私にとっては頭を痛める要因がなくて助かるけれど、防犯としては問題ありだなと思いながら少し行けば、高専から一番近いコンビニが目に入った。意気揚々と店に足を踏み入れた時、室内の明かりに視線を向けてしまったせいで目が眩む。一瞬気が遠くなってふらついた体を支えてくれたのは悠仁だった。目元を節ばった手で覆われて視覚から入る情報が一気に遮断される。落ち着くためにはぁ、とゆっくり息を吐いた。
「大丈夫?一回外出よっか」
密着したことと視界が遮られていることが相まってよりダイレクトに悠仁の声が響く。
「ううん、もう平気。それよりアイス」
しっかりと立ってもう大丈夫とアピールしつつそう言えば、悠仁は食い意地張ってんなぁと笑った。
好きなメーカーのバニラアイスを購入し、スキップしながら店を出る。少し後ろを歩く悠仁を待って、会計をするために離した手を繋げて歩き出した。袋からちらりとパッケージが覗くと、途端にすぐ食べたい気持ちになって急いでアイスを取り出す。
「もう食べんの?」
「うん、今食べたい気分」
いそいそとパッケージを剥いでもらった袋に突っ込み、アイスを口に運ぶ。冷たさと甘みが口いっぱいに広がって多幸感に包まれた。深夜にアイスを食べる、なんて贅沢なんだろう。上質なバニラビーンズの風味となめらかな口どけ、これが罪の味か。なるほど、もっと味わいたい。夢中になってもぐもぐ口を動かしていると、悠仁がこちらをじっと見ていることに気が付いた。ん、と見つめ返すと繋いでいない方の手を差し出される。少し考えて、あぁ、と理解してゴミの入った袋を彼に渡した。正直邪魔だったから助かる。悠仁はこういう細やかな気配りができる男なんだよなぁ。アイスを飲み込んでから「ありがとう」と伝えれば、彼は「いいよ、これぐらい」と笑んだ。
お礼も兼ねて悠仁の口元にアイスを持っていくと、いつものそれより控えめに開けられた口がアイスを攫っていく。もっと持っていってもいいのに。そう思いながら私もアイスを食べると、ふと脳内に疑問が浮かんだ。
「あぁ、そう言えば悠仁はなんであそこにいたの?」
気になったことを聞いてみれば悠仁は「あー……」と煮え切らない答えを返した。教えてよと頬を突いてみると、彼は腹をくくった様子で口火を切る。
「なんか眠れなくって……名前さんに会えたらいいなと思ってさ」
気がついたらあそこにいたと、悠仁が照れた様子ではにかむ。それを見ていたら、どうして自分が懲りずに光を見てしまうのか分かった気がした。
きっと、魅せられてしまったからなんだ。可憐に咲く花のように、輝く宝石のように、強烈に存在を主張するそれに。
「どしたん名前さん、急に。もしかして気分悪い?」
「ううん大丈夫。ただ、少し眩しいなと思って」
手の甲で目を隠す。視覚を失ったことで、一層感覚が研ぎ澄まされていく。脳裏に浮かぶのはもちろん彼のことだ。
悠仁の笑顔はまるで光のようで、私の網膜に焼き付いて離れない。でも私だけがずっと彼のことを考えているなんてずるい。彼も私のことを忘れられなくなればいいのだ。そう、したいと思い立った時は実行するに限る。
そうこうしているうちに男子寮と女子寮を分ける道に辿り着いた。じゃあねと手を振って背を向けかけて、振り返って悠仁に飛びつく。そして、油断して隙だらけの彼の唇を奪ってやった。
「じゃあね、また明日!」
いつだって私を照らしてくれる君に私はとても弱いけれど、負けっぱなしってわけにはいかないのですよ。だって先輩だからね。駆け足で女子寮に飛び込む私の背中に、「あーっ……!」と悔しげな声が響いた。
blue heavenさまに提出させて頂いたお話です。
- 37 -
戻る
