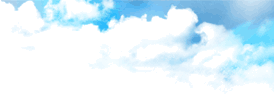
孫と妹の話。明日も一緒に遊んでねと同じ設定。
98話以降を全力で捏造しています。
俺には妹がいる。いや、"いた"が正しい表現かもしれない。この世に生まれ落ちた時から一緒にいた、可愛くて仕方がないあの子は、もう俺の隣にはいない。
俺は、俺たちを引き取って大事に育ててくれた婆ちゃんの家業の手伝いをすることを、かなり早い段階で決めた。婆ちゃんは俺がそうすることに良い顔をしなかったけれど、そこは俺が押し切った。
だけど名前には俺たちが何をしているか知られたくなかった。普通の子どもとして、日々を過ごしてほしかったのだ。婆ちゃんもそう思っていたから、俺たちの家業を名前にはひた隠しにしてきた。
だというのに、ある日名前に知られてしまったらしい。いや、今考えれば多分名前は何も気付いていなかったのだと思う。俺たちが依頼にかかりきりで遊んでやれなかったから、寂しくて隠し事をしていると勘ぐっただけだ。しかしながら、彼女に「お兄ちゃんたち何か隠してるでしょ!」と問われた俺は頭が真っ白になってしまった。
「なにも、隠してないよ」
本当は隠し事だらけ。だからはっきり隠してないと言い切れず、しどろもどろになってしまう。その動揺を名前が見逃すはずもなかった。
「ウソだよ!お兄ちゃんたち、ここ最近ずっと大広間にこもってばっかりじゃない!」
「それは……お客が来てて」
「そのお客さんたちすっごく怖そうな顔して、ドロドロした目してた……」
名前の顔に恐怖が広がっていくのが見て取れる。確かに、ここ最近は血生臭い依頼が多くて、話を持ってくるのも血気盛んな人間ばかりだったから、名前が怖がるのも無理はなかった。
名前の頭を撫でようと伸ばした手が「触らないで!」の叫びと共に叩かれる。ぱしんと乾いた音が虚しく響いた。そんな風に拒絶されたのは初めてで、行き場をなくした手を見て動けないでいると、そんな俺の顔と自分がやったことに驚いた名前がくっと顔を歪めた。
「お兄ちゃんたちのこと、もっと教えてよ!全部一緒に背負いたいのに……!」
それができたらどれほどいいか。でも、優しい名前がこの非人道的な行為を知ったら、きっと心を痛めるに違いない。言いたい、でも言えない。
押し黙るしかない俺にしびれを切らした名前は「もういい!」と声を荒げた。
「お兄ちゃんも、お婆ちゃんも……ッ大っ嫌いだ!」
名前が弾かれたように駆け出していく。その背を追いかけるが、名前は俺を置いてぐんぐん先を走った。そのうち山へ続く道へ出て、鬱蒼と生い茂る木々のせいで名前の小さな姿はたちまち見えなくなってしまう。
すぐに追いつけると思っていた。だけど、名前は俺たちが構ってやれないあいだ、ずっとこの山で遊んでいたのだ。ここはいわばあの子の庭、まともに入ったことがない俺が探し出せるはずもなかった。
昔は転んでは泣いていたのに、いつの間にかあんなに早く走れるようになったんだな。名前の成長がこんなにも嬉しいってこと、早く可愛いあの子に伝えたい。
大嫌いと言った君の方が悲しい顔をしていた。きっと、俺よりずっと傷付いていた。名前のそんな顔はもう見たくない。
ごめんねと謝って、仲直りをしよう。それで手を繋いで、婆ちゃんが待つ家まで帰ろう。だから早く帰ってきて。俺にその姿を見せてほしい。
淡い願いは叶うことなく、次に俺が目にしたのは名前にかけた、呪力を封じる術が解ける音と彼女が履いていた靴の片方だけだった。
頭に何か温かいものが触れたような気がして目が覚める。
「ん……」
緩やかに瞼を押し上げると白い天井が視界に広がっている。体を包み込むのはふかふかの柔らかい布団。薬品くさい匂いもするから、多分病室に寝かされているのだろうと当たりをつける。
「目が覚めた?」
ゆるりと思考を回していると女の声が響く。声の方を見やると、枕元の側の椅子に腰掛ける女がいた。その顔を見て心臓が止まりそうになる。
「名前……!?」
そこにいたのは、あの日失った妹の名前だった。記憶よりずっと大人びているが、紛れもなく彼女だ。どうしてここにと息を吐くような声で尋ねると、名前はゆっくりと口を開いた。
「あの日、家出して、ずっとずっと遠くまで行って、呪霊に襲われたの……そこを五条さんに助けてもらって、今彼の下で呪術師として働いてる」
そこまで言って、名前は苦しげに顔を歪めた。
「お兄ちゃんたちがどういうことをしてたのかも……私分かってる」
その言葉を聞いて、知ってしまったんだなとぼんやり思った。分かっていたのだ、いつかそんな日が来ると。そうなった時、名前にそれまでと変わらず慕ってもらえる自信がなかったから、ずっとひた隠しにしていた。きっと婆ちゃんもそうだったのだと思う。
「私はお兄ちゃんたちの所業を許せない立場で……色々聞かなくちゃいけなくて……でもその前に、ちゃんと言いたいことがあったの」
名前が俯きがちだった顔を勢いよく上げた。
「私、お婆ちゃんとお兄ちゃんの家族でよかった、二人がいたからずっと幸せだった……!」
名前の瞳には涙が溜まっていて、俺とお揃いの虹彩がゆらゆら揺れている。
「あの日、大嫌いなんて言ってごめんね。本当はお兄ちゃんのこともお婆ちゃんのことも大好きだよ……!」
ごめんねと瞳を潤ませる名前を昔みたいに抱き締めてあげたい。背中を優しくさすってやると、名前は安心した顔をしてくれるのだ。その顔が俺にどれほどの力をくれたか、名前はきっと知らない。
「兄ちゃんも、婆ちゃんも、怒ってないよ」
殊更優しく、穏やかな口調で名前に囁く。
「おいで、名前」
両手を広げて呼べば、名前は勢いよく抱きついてきた。しっかり受け止めて、ぎゅうっと強く抱き締める。
「本当はもっと早く言わなくちゃってっ……!でもああして飛び出した手前帰れなくて……!」
「分かってる、大丈夫だよ」
あの日から沢山のことが変わってしまったけれど、名前が泣き虫であることは変わってなくて、少しほっとした。立場や環境が変わっても、俺たちがたった二人の兄妹であることに変わりはないのだ。
堪え切れなくなった涙が肩を濡らしていく。その感覚も懐かしくて、名前の背中に回した腕に力を込めた。
いつか三人で、あの家に帰ろう。
- 33 -
戻る
