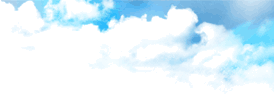
「これ何だ?」
部屋の壁沿いに置かれた大量の段ボール箱を見た伏黒さんがそれを指差しながら聞いてくる。山積みのそれは無視できない存在感を放っているから、疑問に思うのも当然のことだった。ちらりとそれを見やり、「チョコレートです」と端的に答える。
「これ全部か?」
「はい。表向きの仕事もあるので、多くなってしまって」
お邪魔ですよねと言うと、伏黒さんは気にしねぇよと笑った。そうだと呟いた彼が寝転がっていたソファーから起き上がる音が聞こえる。
「俺にチョコはねぇのか?」
作業を行っていた手を止めて、キャスター付きの椅子を動かして伏黒さんを真正面から見つめる。彼はニヤリと口角を上げて私を見ていた。
「貴方、一粒数百円もするようなチョコが食べたいんですか?」
「いや、特には。質より量が多い方がいいな、その方が腹に溜まるだろ」
「そうですか」
はぁと溜息をつく私に、伏黒さんはくつくつと笑った。彼はゆっくりと立ち上がってこちらへ近寄ってくる。彼の節くれだった指先が私の頬を撫で、髪を耳にかけた。その手が私の顎を持ち上げ、彼が腰を折って顔を近づけてくる。
「オマエからのチョコが欲しいって言ってんだよ」
「……まあ、お上手ですこと」
顔は固定されて動かせないから視線だけそっぽを向くと、彼が喉奥で笑った。その態度は気に食わないけれど、数多の女性からチョコを貰っているであろう彼からそれを求められたことは素直に嬉しかった。視線を合わせないようにしながら、伏黒さんの背後を指差す。
「冷蔵庫、開けてください」
「なんかイイもんでも入ってんのか?」
「いいから、早く」
そう急かすと伏黒さんは渋々といった様子で離れていった。椅子を回して机に向き直り、手を動かす。彼が冷蔵庫を開けた音がして、作業をしながら声を掛けた。
「イイものかどうかは分かりませんが、それで良ければ」
今彼の目の前には私が昨日仕込んでおいたチョコたちがあるはずだ。もし彼が、食べきれないぐらい山ほどチョコを受け取ったであろう彼が、私からのそれを欲しいと言ってくれたなら。私も素直になって彼にチョコを渡そうと思っていたのだ。
バリッと派手な音がして、苦心しながら施した包装が剥がされていくのが分かる。もう少し丁寧にしてくれればいいのに。
音がしなくなって、彼が何をしているかを知る術がなくなってしまった。振り向きたくなるけれど、ここでそうすると負けな気がした。耳をそばだてて様子を伺うと、伏黒さんがうまいと呟いた。もちろん味見はしたし、問題なかったから彼に渡したのだけれど、彼にそう言ってもらえて少しホッとした。
口元を緩めていると、気付かないうちに彼が背後まで忍び寄っていた。
「オマエも食えよ」
後ろから手が伸びて唇にチョコレートを押し付けられ、少し口を開いてそれを食んだ。途端広がる、微かな酸味とミルクチョコレートの甘み。これは多分ラズベリー味だと思う。だけど、私はラズベリーの味やその香りのするチョコレートは作っていない。まさかと思って伏黒さんの方を見ると、私のチョコを口に運ぶ彼のすぐ側に小さな缶が置いてあった。淡いピンクが可愛らしいそれは、間違いなく私が欲しいと思っていたブランドの今季限定モデルだ。
「それ……」
箱を指差すと伏黒さんはあぁ、これなと缶を手に取り、目線の高さまで持ち上げた。
「本当、女ってこういうデザインが好きだよな。俺はこんなもん貰っても持ち歩きたくねぇが」
「わざわざ、買いに行かれたんですか」
「あぁ。流石バレンタイン、売り場には女がいっぱいだったぜ」
彼の手にあるそれは百貨店販売限定で、通販はできないものだった。持ち歩きたくないようなデザインのそれを、わざわざ買いに出て、ここまで持ってきたのか。誰のため、なんて聞かなくても分かっている。
「オマエには世話になってるからな」
机に浅く腰掛ける伏黒さんを見上げる。チョコよりも甘い瞳が私を貫いて、この人には敵わないなと思った。
- 24 -
戻る
