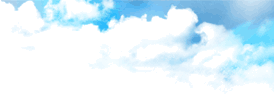
校内を歩いていると、いつの間にか校舎の端の端まで来ていた。校舎の最奥、滅多に人が通らないその部屋には図書室と書かれた古ぼけたプレートが下げられている。ガタガタの引き戸を、音を立てないように気をつけながら開けると、木漏れ日が差し込んで眩しかった。目を眇めて見た先にはロッキングチェアに腰掛けた名前先生がいる。陽に照らされた名前先生の横顔は美術で使う彫刻の人形のようだった。
「名前先生」
声を掛けてから部屋へ足を踏み入れると、先生は読んでいた本から顔を上げて「五条くん」と僕の名を呼んだ。おいでおいでと手招きをしてくれるのを見て、大股で先生に近づいて行く。
「会うのは三ヶ月ぶりだね」
「はい。変わりないようで安心しました」
「まだまだ若い子たちには負けていられないよ。そう言う五条くんは、少し痩せたかな」
先生の言う通り、最後に会った日から体重は一キロか二キロほど落ちた。見た目はそんなに変わらないと思うのだけれど、先生にはお見通しのようだった。流石、長年僕たち生徒を見ているだけはある。
名前先生は僕が高専生の時からここに先生として勤務していて、国語や数学といった一般科目を全て一人で担当している。何でもできるけれど、専門は現代文で、その授業の時だけ口数が多いし、説明には熱が入っているような気がした。そういえば、唯一先生に叱られたのも現代文の授業中だったな。
名前先生は物知りで、いつだって真剣に生徒と向き合ってくれる人で、先生になりたいと言った僕を応援してくれた。
僕が先生なんて変だよねと僕が笑うと
先生はそんなことないよと首を振った。そして、君は良い先生になるよと微笑んだのだ。
「五条くん」
先生に声を掛けられて、過去を遡っていた思考を現代に戻す。なんですかと笑うと、先生は気遣わしげな表情で「最近どう?」とのたまった。
「きちんと休息は取れているのかな」
「大丈夫だよ、昨日は9時には寝たし」
「ご飯は?きちんと三食食べているかい」
「もう、名前先生は心配しすぎ!ちゃんと食べてますよ」
嘘、昨日は急に任務が入って家に帰った時には日は変わっていたし、そうなると食欲より睡眠欲が勝つからさっとシャワーを浴びて寝てしまった。今日の朝ごはんは任務地へ向かう途中で買ったコンビニ弁当で、温めてもらうのを待てるほどの時間もなかったから冷めたご飯をかき込んだ。
こんな生活が先生にバレたら絶対に窘められるに決まっている。いや、それ自体は気にしてもらえてるのだと嬉しいからいいのだけれど。僕が嫌なのは先生に余計な心配をかけることだ。僕は大丈夫、僕は強い、先生にはいつでもそう思っていてほしい。
五条悟は最強で、術師界の要だ。そうでなくてはならない。僕が折れるわけにはいかないのだ。大丈夫、ちゃんと笑えている。いつも通り話せている。
「五条くん」
柔らかな声で、大切なものを呼ぶように僕の名前が紡がれる。慈しむような先生の視線を浴びてちょっと照れくさかった。
「"君がどう見られたいか"と、"君が本当はどういう人か"はまた別の話だよ」
ふふっと笑って、先生は口を開く。桃色の唇が言葉を漏らすのをじっと見つめた。
「君は自身を軽薄でちゃらんぽらんに見せたいようだけれどね、君の近くにいる人間はちゃんと分かっている。君がとても優しいこと、責任感の強い人だということを」
こっちへおいでと先生が呼ぶから、もう一歩踏み込んで先生の足元、ロッキングチェアの脚と床が擦れるのを防ぐために敷かれたカーペットの上に足を崩して座る。
「良い子のことは先生がたくさん褒めてあげよう」
チェアに深く腰掛けていた先生がぐっと起き上がって前へ進む。僕の眼前に誘うように現れた先生の膝に腕を置き、その上に頭を乗せた。
「頑張ったね、五条くん。君はいつも、本当によくやっているよ」
先生の温かい手が僕の頭を優しく撫でる。温い日差しと先生の膝のお陰で押し殺していた眠気が襲ってきた。心地よい微睡みの中、それでもこれだけは言わなければならないと口を動かす。
「先生、あのね。先生が信じてくれるなら、見ていてくれるなら、僕はずっと最強でいられるんだよ」
先生の太ももに少し体重をかける。こうすると先生は重たいよと笑ってくれたのだけれど、いつの日からか何も言わなくなった。呪いのせいで、先生の足はもう何も感じないのだ。僕の重みも、体温も。
先生が僕の頬に手を添える。温かくて柔らかいそれに擦り寄ると先生はくすっと笑った。
「だから、僕より先にいかないで」
眠くて舌ったらずな言葉を静かに聴いていた先生は柔らかく微笑んで、もちろんと頷いた。それを見た途端、瞼が急速に落ちていく。これは多分、先生の術式、催眠だ。久し振りに引っかかっちゃったな、面目無い。先生の穏やかな眼差しを最後に、僕は意識を手放した。
体感五分ほど、僕は深い眠りについていた。瞼を持ち上げ、先ほどよりずっと軽くなった体を起こす。差し込む夕日と本の匂いがいっぱいの部屋の端にあるベッドに寝かされていた。高専時代からこんな部屋は見たことがない。きょろきょろと辺りを見回していると部屋のドアが開き、先生が悠然とした足取りでこちらへ歩み寄ってきた。
「こんばんは、五条くん。気分はどうかな」
「悪くないね。それより、僕どれくらい寝てた?」
「十五分ほどだよ。あまり寝すぎると次に起きるのがしんどいだろう」
「確かに」
うーんと大きく伸びをして、足元に揃えて置いてあった靴を履いてベッドを降りる。サイドボードに置いてあった目隠しを取って身につけた。先生が僕のコートを差し出してくれたから、それを受け取ってさっと羽織る。
「そろそろ時間だから行くね」
「もうそんな時間か。ドアまで一緒に行こう」
見送りをしてくれる先生と並んで歩く。いつもよりゆっくりと歩く先生に合わせて、僕ものんびり歩いた。
僕がいた部屋と図書室はドア一枚で繋がっていて、あっという間に図書室のドアに辿り着いた。ぬくもりのあった部屋から一度廊下に出れば冷たい風が頬を撫でる。
「先生、またね」
「ああ、気を付けて」
先生に別れを告げて背を向ける。ちらりと後ろを見やると先生が笑みを浮かべて手を振っていたから、僕も手を振って返す。僕が突き当たりを曲がるまで、先生はずっとそうしてくれていた。
祓わなければ呪いは進行する。先生の足は何も感じないだけではなく、上手く動かせなくなっているようだと、時々足を庇うように歩く様子から分かった。その呪いは、いつか僕が絶対に解くから。どうかそれまで僕を見ていてね。
- 22 -
戻る
