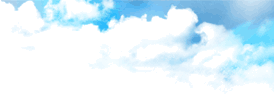
・獄門疆の中の話
・五条が獄門疆について詳しくないという設定です。
傑の姿に気を取られてまんまと封印されてしまった。でもきっとみんながどうにかしてくれるって信じているから、そんなに不安ではなかった。
だけど、この箱の中は退屈で仕方がない。これからどうしようかなと思案していると、突然髪の長い女の子が現れた。ぼんやりと立っているせいか、もしくは青白い肌の色のせいか、透けそうなくらい白いワンピースが何もない空間に浮かんでいるように見えた。さながらホラー映画の幽霊みたいな。今にも空に溶けそうな女の子がゆっくりと僕に向かって何かを差し出した。
「ゲーム……」
「ゲーム?」
意図が分からず鸚鵡返しをすると、女の子は俯きがちだった顔を上げて僕を見つめた。その瞳は深海のように濃い青で、吸い込まれそうなほど澄んでいた。
「ゲームをしましょう」
よく見ると、差し出されていたのはオセロの盤だった。
この子からは呪力も感じないし、そもそもここにいる時点で戦えやしないだろう。それに、どうせ暇だし。
いいよと頷くと彼女はふわりと笑った。
「僕五条悟。君は?」
「#苗字#名前と申します」
石の準備をしながら軽く自己紹介をする。#苗字#ってどこかで聞いたことある気がするんだけどな、どこでだろう。これに封印されるくらいだから、きっとこの子も強いんだろうな。呪術界の重鎮たちを集めた、パーティーと言う名の見栄の張り合いの場で聞いたことがあるのかもしれない。そんな取り留めのないことを考えては消えていく。
「準備が整いました」
「そうだね。じゃあ、」
「えぇ。勝負ですわ、五条くん」
「望むところだよ」
短い会話の後、盤に向き合う。さて、どう攻めようかな。
この子、強い。というか容赦がない。それが分かったのは盤面の八割が白く染まってからだった。ちなみに僕が黒、彼女が白である。圧倒的な僕の負けだった。まだ多少は埋まっていないマスがあるものの、角三箇所を取られ下半分が白一色とは劣勢にもほどがある。もっと言うなら、さっきからパスを選択せざるを得ない状況が続いている。その間にも彼女は勢力を拡大していた。正直勝ち筋が見えない。これは詰みだな。
「降参。僕の負けだよ」
「ふふ、では私の勝ちですね」
「おめでとう。ところで、他のゲームはないの?」
「ありますよ。チェス、囲碁、将棋……」
「じゃあ次は将棋やろうよ」
「いいですね、やりましょう」
彼女がどこからともなく将棋盤と箱を取り出す。カランと音がしたから、箱には駒が入っているのだろう。名前さんがそれを開けるとパカっといい音が鳴って、2人でちょっと笑った。
準備を終えて、早速ゲームを始める。次は絶対に勝つと思いながら、先行後攻を決めるジャンケンをした。
「あー、無理、負けた、僕の負けだよ……」
何この子、めちゃくちゃ強い。将棋もチェスも囲碁も花札も百人一首も、それらを全て一通りやり終えた後嬉々として差し出してきた、なんであるんだと問いたくなる折りたたみ式のゲーム機のソフトでも、ほぼ負けた。唯一勝ったのは今やっている対戦型の格闘ゲームだけ。それも勝率は五割というところだ。
どれも触ったことないソフトだったから、というのは事実だけど言い訳にはならない。彼女だって触ったことないソフトもあったし。
なかなか悔しい。ハメテク使うのずるいって。
「もう一回!僕が勝ち越すまでやるよ!」
「えぇ、受けて立ちますよ五条さん」
ゲーム機に向き合って楽しそうにプレイする彼女が不意に口を開いた。
「貴方もあの脳味噌野郎にやられたの?」
「『も』ってことは君も?」
「ええ。貴方、ここから出たらあいつを木っ端微塵にして頂戴ね」
名前さんの声に少しだけ怒りが滲む。コントロールが乱れた隙をついて彼女のアバターに蹴りを入れると、表示されているライフメーターがゼロになった。
「やった、僕の勝ち」
「はぁ、負けてしまいました……。次に行きましょう」
次のステージを選択する名前さんに、初めて顔を合わせた時から気になっていたことを聞いてみる。
「君もここに封印されてるの?」
「そうね。されていた、が正しいけれど」
彼女はゆるりと口を開いて説明してくれた。獄門に同時に封印できるのは一人だけであること。名前さんにはその辺りの記憶がないけれど、彼女の肉体は既に死んでいること。だから僕が封印できたのだということ。僕が自死しなければ他の誰かが封印されることもないこと。
「貴方なら、他の誰かが封印されるような道を選ばない気がするの。でもそうしたら、貴方は封印が解けるまでひとりぼっちよ」
これほど悲しいことはないわと、彼女は沈んだ声音で漏らした。
「君は寂しかった?」
「……寂しかったわ、とっても」
ゲーム機を握る彼女の手に力が籠る。
ひとりぼっちのこの空間で、彼女の相手をしてくれるのはゲームくらいだったということだろう。そうか、だから彼女はこんなにゲームが上手いんだな。
「私が死ななければ、誰かにこんな思いをさせることなんてなかったはずなのに……」
だから私決めたのと、彼女はゲーム機を置いて真っ直ぐに僕を見た。
「次ここに封印される人が現れたなら、その人を絶対に一人にしない、私が側にいるって」
ある意味呪いだ。とても強い呪い。彼女の固い意志が呪いとなって死後発動したのかもしれない。
死んだ後まで自分を追い詰めなくてもいいのに。君がずっとここにいたのなら、確かに誰かが封印されることはなかっただろうけど、君はずっと一人で苦しまなくちゃならなかっただろう。
「そんなに思い詰めなくていいよ」
怪訝な顔をする彼女に「現代には信頼できる僕の仲間がいるからさ」と笑いかける。
「だから名前さんも僕の仲間を信じて」
名前さんの硬く握られた拳にそっと触れる。冷たく強張ったそれをほぐすようにゆっくり指を一本ずつ絡めた。
ここから僕が出たのなら、名前さんは役目を果たしたことになる。そうしたら彼女も、ずっと行きたかった仲間のところに心置きなく迎えるだろう。そんな日がすぐに来るといい。だからみんな頑張ってね。この僕と、僕に勝った名前さんが応援してるからさ。僕の眼にはずっと、外のみんなの勝利が見えているよ。
握られた手には確かな力が宿っていた。
- 19 -
戻る
