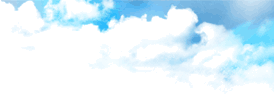
高専時代の話
最近夏油先輩は落ち込んでいるというか、いつもの覇気がないというか、元気がないなぁと思うことが増えた。私には何もできないけれど、私が能天気に先輩に話しかけることで少しでも彼が癒されてくれたらいいなぁと思う。
シャワーを浴びてさっぱりして、共有スペースでまったりしていると前方から夏油先輩がやってきた。
「夏油先輩、お疲れ様です!」
「やあ名前、何か飲むかい?」
自動販売機の前に立った先輩が笑いながら聞いてくれる。奢ってもらうだなんて申し訳なくて胸の前で手を振ると、「遠慮しなくていいよ」と先輩が笑ってくれた。それならばとアイスの紅茶をお願いしてみると、先輩は私が欲しいと言った紅茶の下のボタンを押した。間も無く紅茶の小さいペットボトルが落ちてくる。
「はい」
「ありがとうございます」
「どういたしまして。隣座ってもいいかな」
「もちろんです!」
ペットボトルを受け取って左へずれると、微笑んだ先輩が隣に腰を下ろした。
「いただきます」
「どうぞ」
手を合わせてからペットボトルの蓋を開けて少し飲んだ。ミルクティーのほのかな甘みが口の中に広がっていく。
飲み終えて蓋をして隣をちらりと見ると、先輩が先ほど購入していたお水を飲み終えたところだった。
「調子はどう?」
「絶好調、というわけではないですが、良い調子だと思います。夏油先輩は最近なんだか元気がないですね……?」
「夏バテ気味なだけだから気にしなくていいよ」
先輩の少し沈んだ様子に何か言おうかと迷っていると、それより、と先輩が話を変えた。
「今日は遠出だっただろう、疲れたんじゃない?」
「大丈夫です!ただ昇級試験も兼ねてたらしくて……でもベストは尽くしました」
「そうかい。名前ならきっと大丈夫だよ」
先輩の手が私の頭の上でポンポンと跳ねる。先輩にこうされるとドキドキして、ぽーっとしてしまう。
先輩を見つめていると、彼が少し迷うそぶりを見せて、ゆるりと口火を切った。
「名前、呪術師を続けるのは辛くないかい。昇給するということは更に危険な任務につくということだ。怪我をするかもしれないし、最悪生きて帰ってこられないかもしれない」
呪術師なら誰でもあり得る、最悪の可能性。
なんと返すか考えて、私はゆっくりと口を開いた。
「怖くないと言えばうそになります。だけど私は、あの日私を助けてくれた夏油先輩のように、誰かを助けられる人になりたいんです」
あの日、呪霊に襲われて死を覚悟した時、夏油先輩に助けてもらったのだ。強大な敵に堂々と立ち向かう先輩の背中に憧れた。
「だから、呪術師を続けるのは辛くないです」
はっきりと告げた。曇りのない、私の本音だったから。
「私も夏油先輩のようになれるでしょうか」
か細い声が2人の間に満ちていく。
突然夏油先輩に抱き締められて驚いた。鍛え上げられた肉体を直に感じて、私は先輩の腕の中で固まった。身動ぎひとつできないでいると、先輩が「大丈夫」と囁いた。
「名前はもう充分、沢山の人を助けているよ」
先輩の声が少し震えているような気がして、だけどそれを指摘したら何かが終わってしまう気がして口を噤んだ。胸がいっぱいで泣いてしまいそうだった。
- 15 -
戻る
